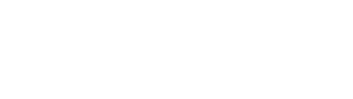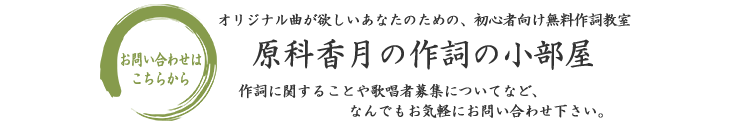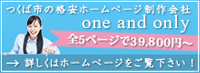創作の小部屋「函館物語」第1回
2022年01月22日
 創作の小部屋「函館物語」第1回
創作の小部屋「函館物語」第1回
今朝の新聞一面は「まん延防止5県追加へ これで29都道府県に拡大」とあります。この5県には、私の住む茨城県も含まれています。
それにしても、飲食業関係の方々には、かける言葉が見つかりません。暮れから正月にかけて、もう大丈夫だと思った矢先のオミクロン株。本当に安心して、外出や食事を楽しめる日はいつやってくるのでしょうか?
話は変わりますが、正月明けの6日でしたか関東でも大雪が降りました。我が家の辺りも真っ白な風景となりました。茨城の人は雪道には慣れていないものですから、私が散歩している僅かな時間に、何台もの車がスリップして、車道のブロックを越え歩道に乗り上げておりました。怪我人はいなかったようで安心致しました。
つい先日は、海の匂いが嗅ぎたくなって、急遽、鹿島港までドライブしました。
釣り宿が港内に沢山ありましたので、ちょっとお話を伺いました。現在は、太刀魚が好調で50匹以上釣れていると申しておりました。画像は、船釣り客が、港内に併設されている「魚釣園」の釣果のなかった人に分けてあげた太刀魚です。大きさは優に70cmは超えておりました。
本日から、「函館物語」という長文を書いて見ることに致しました。先ほど第1章を書き終えてのアップです。今後のストーリーはまだ決まっていません。皆さんに喜んでいただけるような物語を書けたらと思っています。
創作の小部屋 函館物語
第1章 故郷への回帰
昨夏、古希を迎えた私は、一度も結婚したことがない。恋愛の経験がないわけではない。若い日、私はある人に夢中になった。彼女も私に好意を持ってくれ、将来を誓い合った。だが、結ばれなかった。彼女の名前は、坂本真知子と言った。
今、私は函館山の頂上にいる。彼女と一緒に登ったのが最後だから、実に半世紀近くの歳月が流れただろうか?私は、この思い出の地である函館に、東京のマンションを引き払い数日前に帰ってきたばかりだった。
函館に帰った私は早々に、昔の職場の友人の佐々木に、私の愛した彼女の近況が知りたくて電話を掛けた。友人は私からの電話に大喜びをした。しばらくは、昔話に花が咲いた。私も友人との会話は懐かしく、いくら時間があっても足りないと思えた。しかし、彼女が今どうしているか、それが早く知りたかった。
「聞いた話なので詳しいことは分からないが、彼女は一生を独身で通したようだ。60歳を少し過ぎた頃に乳がんを患い、かつての病院に入院していたが、暫くしてから亡くなったらしい」
友人は私と真知子さんのことは知らない。過ぎた昔話のように感情のない話し方だった。
話しの途中ではあったが、溢れ出る涙に、一言礼を言って私は急いで電話を切った。
彼女も、生涯を独身で通したのだ。あの時の二人の愛は確かなものだった。それ故に、結婚してもよいと思える異性には、私も彼女も生涯巡り合えなかったのだ。いや、比較などではない。どんな異性も、恋愛の対象とさえもなり得なかったのだ。
今見つめる函館山からの夜景は、眩し過ぎる光が函館駅を中心に輝いている。その美しさは、あの日とほとんど変わらない。その光が歪んだ。辺りには人影がなく、私は頬を伝う涙を拭おうとはせず、流れるままに任せた。友人から彼女の死を聞いたあの時から、私はなぜもっと早く帰らなかったのかと自責の念で一杯だった。
彼女との函館山での思い出が昨日のように私の脳裏に蘇る。
「真知子さん、本当にこの函館山からの夜景は素晴らしいですね。僕は、今日のこの美しさを生涯忘れないつもりです。今日は、付き合ってくれて本当にありがとう」
真知子さんは、キラキラした瞳をうつむき加減にして微笑んだ。
「私も、忘れないわ。私は、この夜景は幼い日から何度も見ているけれど、今夜の夜景が一番輝いて見える」
真知子さんは、私の目を真っ直ぐ見ながら言った。
いつの間にか、二人は手をつないでいた。私は、抱きしめたかったけれど、付き合い始めて日が浅く、まだ早いと自らを律した。真知子さんの手の指は、細くて白かった。
「真知子さん、あまり遅くなると、お家の人が心配するといけないから、そろそろ帰ろうか」
私は、本心ではなかったけれど、つい口に出した。真知子さんは、腕時計を見ながら言った。
「あら、こんな時間?じゃあ、次のロープウェイで降りましょうか」
ロープウェイの乗り口に差し掛かるまで、お互いに無口だった。近くには誰もいなかった。不思議なことに、彼女がいきなり私の胸に顔をうずめた。
「私、帰りたくない。このまま、ずっといたい」
彼女の唐突な態度に、私はたじろいだけれど、両手で彼女を抱きしめた。私も、ずっとこのままいたかった。それでも私は、冷静だった。今は、彼女の家族に嫌われるような、心配をかけるようなことは、極力避けるべきだと考えた。私と彼女の生きる世界が大きく違っていたからだった。
「真知子さん、今度の日曜日、もし用がなかったら、五稜郭を案内して貰えない?中学生の時に一度、友達と行ったことがあるけれど、ワイワイ騒ぎながらだったんで殆んど記憶にないんだ」
彼女は、私の胸から顔を上げた。
「大丈夫、10時ころ五稜郭タワーの前で待ってるわ」
真知子さんの顔は、周りのライトに照らされて、薄桃色に浮かび上がった。
その時の声は、今でも鮮明に覚えている。思い出は後からあとから、溢れる涙と共に浮かんでくる。彼女の甘い香りが鼻先に漂うような錯覚がし、言いようのない寂寥感に襲われた私はいつまでも泣き続けた。
確か「夜景の函館山」でのデートは、この時が3回目だった。初めてのデートは、「立待岬」だった。
私の名前は、高橋春彦。生まれは、函館の西側に隣接する町で、現在は北斗市と呼ばれている。生家は海岸に近く、幼いころは夏になると真っ黒になりながら、岩陰の小魚を捕り、短い夏を楽しんだ。
父親は、家からそう遠くない小さな町工場にオートバイで通勤していた。母は近くの小さな漁港で、漁師が捕ってきた魚の選別や雑役などをしていた。決して裕福な家庭ではなかったが、父も母も私たち兄妹を、愛情たっぷりに育ててくれた。
真知子さんは、函館生まれで、大きな邸宅に住む資産家のお嬢さんだ。父親は、数十人の社員を持つ建築会社を経営していた。また函館商工会議所でも一目置かれる存在だった。当時は好景気で、益々会社は成長していたようだ。彼女は、一人っ子として両親の寵愛を受けて育った。
私と真知子さんは、同じ函館市内の病院で働いていたのだった。私は放射線技師で、彼女は薬剤師だった。
私は、放射線技師になる前は、東京の南に位置するある家具製造会社で働いていた。次回は、工場の作業員からなぜ放射線技師になったのか、そして真知子さんとの出会いまでを、記憶を手繰り寄せながら記してみたいと思う。 つづく
≪お詫び≫ 大変申し訳ありませんが、私はしっかりした調査をせずに大きな誤りを致しました。それは「道南いさりび鉄道」の設立時期を間違えたことです。平成26年を昭和26年と本当に恥ずかしい間違いをしてしまいました。文中の誤りの部分は削除させて戴きました。申し訳ありませんでした。
〖注〗アイキャッチ画像と一番上の「五稜郭タワーから眺めた函館市街と函館山」はウィキペディア様から、「函館山からの夜景」及び「五稜郭」の画像は、北海道観光公式サイト様からお借りいたしました。