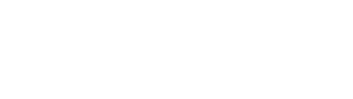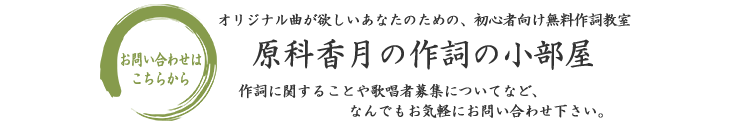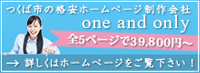創作の小部屋「独居老人のひとり言」第1回
2019年03月28日
 「独居老人のひとり言」第1回
「独居老人のひとり言」第1回
ここつくば市の桜はまだ咲いてはおりませんが、昨日見たピンクの蕾は大きく、今日あたりから咲き始めるのではと思いました。北国の方には、待ちかねた春がやっとそこまで来たという感じです。
さっそくですが、本題に入ります。私もとっくに還暦を過ぎあと数年で古希を迎える年となりました。世間では超高齢社会化の問題についていろいろ取り上げられています。私にはこうした現代社会の問題について述べるだけの見識はありませんので、当の老人の立場から私なりの思いを短編小説の主人公の口を借りて述べてみたいと急に思い立ちました。
今朝5時に起きて書き出しました。下書きなしのいつものぶっつけ本番なので、文章が1人称だったり3人称になったり、纏まらないかとは思いますが、挑戦してみたいと思います。内容は思い付きですので、脈絡や整合性に注意しながら、進めていきたいと思います。
「独居老人のひとり言」第1回
序章 中学卒
私は中学しか出ていない。特に勉強が嫌いな訳ではなかった。強いて言えば、私はどっちかというと勉強が出来る方だった。
私には3つ上の姉がいるが、この姉は私など問題にならないくらい勉強が良く出来た。私の記憶にある姉は、家の農業を手伝っている時か、炊事や掃除をしている時以外はいつも勉強していた。
私が小学校の4年生の夏の時のことだから、今から60年近くも前のことになる。当時、私の家の裏庭にはぶどうの木があり、薄緑のぶどうがたわわに実っていた。姉はその裏庭に小さな机を向けて勉強していた。私は悪戯心でそっと姉に近寄り、「わっ!」と大きな声で驚かした。勉強に集中していた姉は、烈火のごとく私を怒った。
いつも勉強している姉だから、通信簿には5の数字ばかりが並んでいた。姉が中学3年のとき、世間では正月の気分もやっと抜け出したと思われる頃、姉の担任の教師が家にやって来た。土間の板の間に腰を降ろし、教師と父親は何やら話し合っていた。姉と私は、畳の部屋で二人の話を聞いていた。母は話には加わらず、静かにことの成り行きを見守っていた。
小学生の私にも、話の内容は理解できた。教師の話しを要約すると、姉がこんなに成績が良いのに高校に進学しないのはもったいない。ぜひ、高校に行かせて欲しいというようなことだった。教師も私の家が貧乏なのを知っているので、奨学金の話しも熱心に説いた。
昭和30年代の田舎の農家はどこの家も貧しく、男も女も中学だけで就職する者が大半だった。まして女は、無理してまでも高校に行かせることは無いというような封建時代の風潮がまだ残っていた。
担任の教師が奨学金の話までし、何とか高校へ行かせて欲しいと熱心に説いたにも拘らず、両親は姉に就職を強要したのであった。姉の話しを聞いた担任の教師は、2度3度と家にやって来たが、父親は苦虫を噛み潰したような顔をし、教師に頭を下げて、感謝の言葉と意に添えない不甲斐なさを詫びていた。
貧乏とは、辛いものである。この頃だったと思うが、中学生の姉と私が同じ日に音楽の授業があった。私のクラスの者はハーモニカを持参するよう、担任の先生から言われていた。当日、家に一つしかないハーモニカを引き出しから持って学校に行こうとしたが、姉に取り上げられた。学年トップの成績優秀の姉が、やはり使う筈のハーモニカを持たずに、音楽の授業に出ることは所詮無理な相談だった。私は、大きな声で泣いたのを覚えている。
姉についての結論を言うと、姉は家の状況を理解していたので、涙を飲んだ。いや正しくは、初めから諦めていたのである。
ここまでの話で、私が何故中学しか出ていないのかおおよそ理解して頂けることと思う。もちろん奨学金のことは、姉の中学の担任の先生の話を覚えていたので知ってはいた。けれども、貧乏という匂いは、ハーモニカの件だけでなく、意識と体に染み込んでしまっていて、姉と同じように諦めていた。でも、多少負けず嫌いの私は、クラスで3番から5番位の間でそれなりの成績は残していた。確かに、この頃になるとどこの家の生活も少し良くなり、進学するものも大分増えては来てはいたが。 つづく