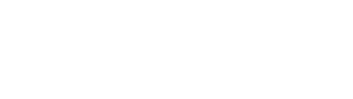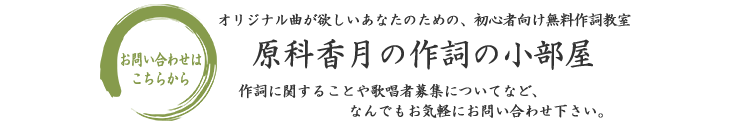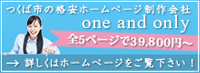創作の小部屋「独居老人のひとり言」第2回
2019年03月28日
 「独居老人のひとり言」第2回
「独居老人のひとり言」第2回
超高齢社会を含めた現代社会について、高齢者の私が短編小説の主人公の口を借りて、思いつくままお話をさせて頂きます。誤字脱字や脈絡・整合性に誤りがあれば後日修正させて頂きます。
「独居老人のひとり言」第2回
第1章 妻との結婚そして死別
私は、近くに新しくできたゴム製品の製造工場の工員となって働くことにした。父親の勧めでもあった。姉の時とは違い私の成績からして、特に担任の教師が家に来て進学を勧めるようなことは無かった。
私は中学卒という学歴を特に恥ずかしいと思うようなことは無かった。何故なら、周りは皆同じような人たちばかりだったからだ。日勤と夜勤の交代勤務も、10代の若い自分はたいして苦にもならなかった。ただ、朝の自転車での通勤時に、中学の時の同級生が制服を着てさっそうとバス停に向かう姿に出来わすときは、何故か下を向いて通り過ぎた。
働き始めて5~6年たった頃だと思うが、今は亡くなった二つ年下の妻と職場で知り合い、2年付き合ってから結婚した。二人とも若すぎたが、双方の親も許してくれた。妻は、私が夜勤の時はいつも美味しい弁当を作ってくれた。とても幸せだった。家を持とうねと二人で決意し頑張って働いた。
その甲斐あって、それから8年後に小さな建売住宅を購入した。60坪の土地と27坪の家は、二人の愛の住処となった。建売住宅は田舎のことなので思ったよりも安く、その家のローンの支払いも二人で働けば十分楽に返せた。子供は家を購入した翌年に、男の子が生まれた。この時代には珍しく、工場の責任者は6ヶ月の育児休業を許してくれた。この頃の私は、多分妻も同じだと思うが、幸せの絶頂だったと思う。私は、妻を愛していたし、子どもの育児にも真剣に関わった。妻の母親も、妻が働きだすと保育園の送迎など積極的に応援してくれた。
お気付きだと思うが、私はもうすぐ古希を迎える高齢者である。私が愛した妻は、私が還暦を迎える年、もう直ぐ定年退職という頃に病で亡くなった。癌であった。
私が言うのも変だけれど、妻はとても頭の良い人で、中卒にも拘わらず工場の事務職に抜擢された程だった。家では、忙しい仕事や家事の合間にはいつも本を読んでいた。
私には、医学のことは分からない。妻が、食欲がないと妙に瘠せ始めてから、近くの医院に行って何かの薬を貰ってきた。しかし服用しても一向に改善せず、それから1ヶ月も経った頃、バスで国立の病院に行き診察を受けた。その日は、検査の予約をしただけとのこと。私は、何かとても嫌な予感がしたのを覚えている。
数回の検査が済んで何日かたった土曜日の夕方、突然居間の電話のベルが鳴った。妻の担当医からの電話だった。妻は、2階の部屋で本を読んでいた。担当医は、妻がこの時間帯はいつも2階で読書をしていることを聞き出していたので、初めから私が電話口に出ることを予想していた。何日の何時に病院に来て欲しいということだった。検査の結果を詳しく説明したいとのこと。妻にはまだこのことは知らせないで欲しいという。メモを取り、電話を切った途端に眩暈がした。
それからのことは、私にはあまり記憶がない。担当医の説明にも、癌についての何の知識も持ち合わせていない自分は、ただ緊張しながら「先生にすべてをお任せします。何卒よろしくお願いいだします。」と、茨城弁の抑揚で下を向いて話すことしかできなかった。医師の説明も、帰りの車の中では殆ど覚えてはいなかった。ただ、妻の明子の今後の行く末に、暗雲が立ち込めていることは確かのようだった。
手術の前日、息子夫婦が遠い四国から飛行機で帰り、私の車で一緒に病院に向った。息子夫婦には、前もって病名を知らせておいたせいか、とても不安げだった。しかし、妻にはあくまでも秘密と固く約束した。3人でため息とも取れる小さな声を発した。
病室の妻は、ニコニコとしており、とても手術を明日に控えた者とは思えない姿だった。妻は、もともと私よりも人としての器が大きかった。そのお蔭で、どれだけ救われたか計り知れない。翌日の手術室に向う時も、笑顔で私たちに手を振った。
手術後いったん回復したかのように見えたが、半年後にまた体調を崩し、再入院となった。主治医の話しだと、癌は取りきれた筈だったが、目に見えない小さながん細胞が妻の体の中を駆け巡ったらしい。抗がん剤・放射線療法とその治療のせいか、髪の毛が抜け、頬はこけて、日に日に妻の体はやせ細って行った。私は、自分の体と取り換えることが出来たらと、何度家に帰ってから涙を流し続けたか知れない。
妻はやせ細って、次第に意識が遠のく状況を繰り返しながら、2ヶ月後に亡くなった。妻は、まだ意識がはっきりしているうちにと、私を枕元に手招きし、やっと聞き取れるくらいの小さな声で、私の耳にささやいた。
「お父さん、今までありがとうね。お父さんと一緒になれて幸せだった。結婚して本当に良かったと思っている。後悔したことなんか、一度も無かった。もし、私が死んでも長生きしてね。幸喜たち夫婦は田舎に呼ばないで、自由にさせて欲しい。ただ、お父さんが一人でご飯を作ったり、洗濯したり、ちゃんと出来るかそれが一番心配・・・。私の分まで、長生きしてね・・・。本当にありがとう!」
そこまで言うと、疲れたのか小さく深呼吸をし、微笑んだ。もう、思い残すことは無いというふうな、安ど感に満ちた表情をして、私の手を握った。妻の指は白く細かった。 つづく