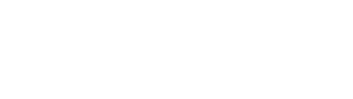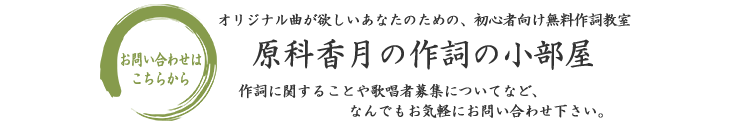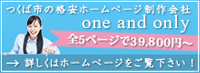創作の小部屋「函館物語」第6回
2022年02月20日
 創作の小部屋「函館物語」第6回
創作の小部屋「函館物語」第6回
13日は関東地方も雪が降ると言われていましたが、平地は殆んど降りませんでした。翌朝、筑波山を見ると白く光っていましたので、近くまで見に行って来ました。(クリニックして大画面にてご覧ください)
青空に凛々しく浮かぶ筑波山も大好きですが、こうして年に数回あるかないかの雪の姿も趣があって好きです。田んぼは、この季節は色彩のない薄茶色ですが、全体から見ますと風景にマッチしているようです。
筑波山だけでは少し殺風景なので、椿の画像もご覧いただきます。先ず乙女椿です。
白椿です。雪が降っても負けない、とても寒さに強い椿ですね。
それでは、「函館物語」第6回をご覧いただきます。
創作の小部屋「函館物語」第6回
第6章 私の職場内での配置転換
4月に入職し、まだ半年も経たない9月から、レントゲン技師長は、私を「消化管造影検査室」への勤務を命じた。予約がだいぶ先まで埋まっている「消化管造影検査室」を充実させたいと、技師長は私に言った。院内でも問題となっているらしい。
当時の私の病院でのレントゲン技師が携わる業務は、主に以下のようであった。
〇一般Ⅹ線撮影 〇消化管造影検査 〇 血管造影検査 〇超音波検査 〇 シンチグラフィ
私が入ったばかりの時は、CTスキャンの機械はまだ導入されていなかった。高額でもあり、まだ設置されている病院は少なかった。だが2年後には当院にも設置された。
私の勤務している病院の患者数が、外来及び入院患者ともに、ここ数年大きく増加しているらしい。近い将来増築の計画もあるそうだ。確かに、1階の正面受付は人混みで溢れ返っている。
私の命じられた「消化管造営検査室」は、バリウムを使っての胃や腸の画像を撮影するのが主な仕事だ。簡単に言うと、バリウムを患者さんの体内に入れて、色々な角度からの胃や腸の写真を撮る仕事だ。どの検査もそうだろうが、特にこの検査は技師の力量が問われる。医師の確定診断をも左右するからだ。一朝一夕に、医師の求める質の高い画像を撮るのはとても困難だ。
放射線の学校で、「胃や腸のバリウム検査を受けた人の声」というテーマの授業を受けたことがある。バリウムの検査を受けた患者は、主に以下のような思いをしているようだ。
◎患者にとり、胃や腸のバリウムでの検査を受けるのはとてもストレスになる。とても辛いからだ。ゲップをするなと言われても高齢者は我慢できない。
◎胃も腸もどちらの検査の場合も、ガラス窓の向こうから、右に回ってとか左に回ってとか、体の向きを技師に指示される。しかし、それでなくても緊張している状態だというのに、どっちが右か左か分からない。焦らせないで欲しい。
◎胃の検査の場合、逆さのような状態での撮影は、台の上から落ちないかと恐怖で一杯になる。血圧の上昇も気になる。
◎腸の検査おいては、バリウムと空気をおしりから入れられ、お腹が張ってとても苦しい。その上、体の向きを変えるのは本当に辛い。
◎胃も腸も検査が無事済んでも、その後はトイレでのバリウムとの戦いになる。胃や腸の中で、バリウムが固まってしまわないかと不安になる。
◎レントゲン技師は患者の気持ちを考えて、もっと優しく丁寧に接してほしい。
これらの意見はどれ一つとっても間違いではない。だが、技師にも都合があるのも分かって欲しい。時には、多くの患者が後につかえている。悠長に優しくなどとは言っていられない場合もある。もちろん患者が主役であることは承知している。
この難しい造影検査の業務を任された私は、少しでも患者さんの辛さを軽減できるような技師になりたいと思った。だが、突然今日から一人前になれる訳ではない。暫くは熟練の先輩の指導を受けながらマスターすることになる。早く消化器の医師に認められるようになりたい。そして、患者さんに安心して検査を受けて貰える技師になりたい。そう思った。
世の中、日進月歩である。もちろん医学の世界も同じである。だがその進歩は、決してスポットライトを当てられながらのものではない。痺れるような涙ぐましい先駆者の苦労があってこそだ。それは、今度私が担当となる、消化管造影検査もまた同じだ。
〖ある医師の命の信念〗
私は、放射線の学校で「二重造影法」という撮影法を学んだ。それは、それ以前の撮影方法よりも、胃や腸の内壁をより精密に撮影できる方法だ。この撮影法が、日本における胃がんの早期発見を飛躍的に向上させる原動力となったという。その撮影法を研究・確立させた医師については、以下に記す。
その医師は、昭和20年代後半から30年代にかけて、まさに命をかけた凄まじい研究の末「二重造影法」という撮影方法を確立させたのである。その医師の名は、後に順天堂大学教授となった白壁彦夫という。研究当時の、千葉大での凄まじい努力、また功績については「ガン回廊の朝」(柳田邦男著)という本に詳しく記してある。
その「ガン回廊の朝」から、白壁医師の涙ぐましいその姿を覗かせて頂く。
当時、昭和20年代後半から30年代にかけての話しである。白壁医師は、千葉大学の第一内科レントゲン室に所属していた。彼は、夜は毎晩1時ごろまで研究室にこもり、下宿に帰ってからは、持ち帰った医学の文献を読むという生活を日常的にしていた。
外科から切除標本を借り、片っ端からバリウムを詰め、術後のⅩ線検査をした。バリウムの量・空気量・圧迫の有無など考えつく限りを尽くし写真を撮った。即ち正確な診断のための撮影技法の研究に明け暮れたのである。その研鑽が功を奏して、二重造影法という撮影技術を編み出したのである。当時は、まだレントゲン写真から早期の胃ガンを見つけることなど困難な時代であった。
ある日、白壁医師は、胃の不調でやって来た患者に小さなガンを見つけた。二重造影法で初めて見つけた初期のガンである。白壁医師は、自分を評価してくれていた外科教授に報告すると、教授が執刀してくれることになった。だが、いざ教授が開腹したが、ガンは見つからず、教授は手術を諦めた。閉腹と告げた。
しかし、白壁医師は、「いえ、でもお願いします」と青い顔をして懇願した。教授の意見に反論することなどあり得なかった時代である。もし、病巣がなく開腹したとなると、外科の責任、即ち外科の教授の大変な落ち度ということになる。白壁医師は内科である。
教授は、病巣がある筈の部位を何度も触診したうえで、白壁医師に更に繰り返し聞いた。
「なあ、もういいだろう?」
閉腹してもいいだろうという意味である。白壁医師は、緊張して小刻みに震えながら、その場にいた医師たちも信じられないような言葉を口にした。
「でも・・・お願いします」
手術は時間との闘いである。教授が、閉腹と宣言してから5分の時が過ぎている。手術室は息が詰まるような緊張感で包まれた。
「ないよ、君、困ったよ!なあ、いいだろ!」
教授は苛立ちながら言った。それでも、白壁医師は態度を変えなかった。それどころか、驚くような言葉を口にした。
「いえ、先生、切ってください!」
白壁医師の鬼気迫る姿に、教授は覚悟を決めた。手術を再開したのである。
その結果、剔出(てきしゅつ)された胃の臓器には、触診では判らない程の小さなガンがあったのだ。千葉大医学部では、これ程小さなガンの手術は初めてのことだった。本来は外科の貴重な標本となる筈だったが、教授は白壁医師に臓器を差し出した。教授もまた真の医療人であった。
私は、この「ガン回廊の朝」を何度も読んだ。この場面では涙が止まらなくなる。私は医師ではなく、放射線技師である。だが、後世に名を残すような人生でなくとも、医師に頼られる、そして出来る限り患者に寄り添うことのできる技師になろうと誓った。
約1ヶ月が経った頃、レントゲン室に患者のレントゲン写真を取りに来たある外科の医師が言った。
「高橋君、最近の写真は良くなったね。土井君に近づいたよ」
私には到底信じられる訳はなかった。この仕事は奥が深い。1ヶ月程度の経験で一人前になれるなら誰も苦労はしない。この外科医は、私が土井先輩から勤務時間の後も遅くまで指導を受けているのを知っている。また、図書室から土井先輩の推薦の「消化管造影検査」の類の多くの書物を休日に学んでいることも知っている。
私を励まそうとのリップサービスだ。だが、この医師には悪意はない。大分先まで埋められた予約表の緩和のためには、熟練した技師の誕生が一日も早く望まれている。私も少しでも早く期待に応えたいと考えていた。
傍にいた土井先輩は、ニコニコしている。人間としての器も大きい、この先輩の力なくして私の成長はない。
レントゲン技師と消化器外科医との、合同での胃部レントゲンフィルムの読影会がある。その時でも、土井先輩は医師と同等に渡り合う。ある時などは、医師が気付けなかったスキルス性の陰影を指摘し驚かれたこともあった。早く土井先輩の力量に追い付きたい・・私はそう強く願った。私の土井先輩への畏敬の念は更に深まった。
ここしばらく、慣れない仕事での疲れと休日の勉強で、真知子さんとのデートの頻度も少し減った。そういえば、真知子さんと行った2回目のデートの「見晴公園」の話しはまだ書いてなかった。遅くなってしまったけれど、次回報告させて頂くことにしたい。 つづく
※二重撮影法とは、陽性造影剤と陰性造影剤の併用による二重のコントラストを利用するⅩ線検査法である。端折って言えば、検査部位においてバリウムと空気を混じり合わせるよう何回も体位交換を行い、検査部位の粘膜にコントラストをつくる撮影法である。このことにより粘膜の細かい異常も発見しやすくなる。
【お詫び】文中で使用させて頂きました造影剤撮影装置の画像は「湘南クリニック」様のものです。ウィキペディア様のページからお借りしました。イメージ用をして使わせて頂きました。有難うございました。