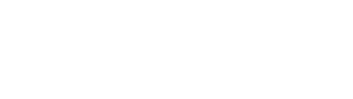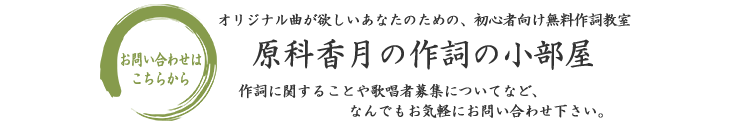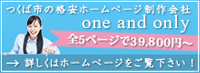創作の小部屋「函館物語」第16回
2022年04月24日
 創作の小部屋「函館物語」第16回
創作の小部屋「函館物語」第16回
今日のつくばは曇り後雨という予報です。この時期は、農家は忙しくなります。もう直ぐ田植えの季節だからです。昨日散歩しながら撮った画像をアップしています。上の画像はいつもの散歩道です。農道を歩いていると沢山の鳥の声が聞こえて来ます。ひと際、ひばりとウグイスの声が響いてきます。
下の画像は、代掻きを終え、もういつでも田植えが出来る状態のたんぼです。
この画像は以前撮ったもので、代掻きの様子です。西風の強い夕方でした。
途中、竹林の中にタケノコが見え、思わずシャッターを切りました。
我が家の道路側の花壇に咲いたアイリスの花です。
今朝の某新聞朝刊に、北方領土「露が不法占拠」との見出しの記事が載っていました。外務省の2022年度版外交青書において北方領土は「日本固有の領土であるが、現在ロシアに不法占拠されている」と記述しました。
この時期の急なこの強気な姿勢には、私は一抹の不安を覚えます。
創作の小部屋「函館物語」第16回
第16章 別れの青函連絡船
真知子さんは、来てくれるだろうか?
約束の日曜日、私は何と9時過ぎに市電函館駅前に着いてしまった。昨夜は少しも眠りに就いた気がしなかった。ウトウトしては目が覚め、その度ごとに真知子さんが来てくれるように祈った。
何をするでもなく、近くをウロウロして時間の過ぎるのを待っていた。どうして楽しい時間は過ぎるのが早く、そうでない時は遅いのか?腕時計を何度見ても、時計の針はいくらも進まない。
私が真知子さんに伝えた10時まであと数分という時、私のすぐ近くに国産の高級車が滑るようにして停まった。私に縁のない高級車には興味がなかった。私は、また腕時計を見てため息をついた。
「お早うございます!」
運転席から、何と真知子さんのお母さんが降りてきた。私は思わず挨拶も忘れ、真知子さんのお母さんの顔を見つめた。
「晴彦さん、ここは車の通りが激しいので、少しお話し出来る所まで付き合ってもらっていい?」
真知子さんのお母さんは、助手席のドアを開けてくれた。高級車はやはり内装が違うなと、革張りの椅子に身を沈めながら一瞬思った。こんな時に俺は何を考えているのだと自分を叱った。真知子さんはどうして来ないのだろう?なぜ、お母さんなのか?真知子さんのお母さんは、私に何を話そうとしているのか?
車の中の真知子さんのお母さんは何も話さなかった。5~6分も走っただろうか。青函連絡船の乗り場近くの、港のよく見える空き地に車を停めた。やっと真知子さんのお母さんは口を開いた。
「晴彦さん、ごめんなさいね。本当は真知子が来ればよかったんだけど、昨夜から食事も摂らないで部屋の中から出て来ないんです。
夕飯だよと下からいくら呼んでも来ないものだから、真知子の部屋に行くと、ベットの中にうずくまって泣いていたんです。どうしたのと聞くと、明日、晴彦さんから会わないかと誘われているけど、私はもう晴彦さんとのことは諦めているので、行けないと言うのです。
でも、晴彦さんを待たせたら可哀そうだから、とにかく会ってきたらと私が申しますと、真知子は私にしがみ付いて泣きじゃくるのです。
真知子が余りにも可哀そうで私もついもらい泣きをしてしまいました。真知子は、どうしても晴彦さんを諦めようと、無理をしているのが母親の私には分かりました。
晴彦さんは既に察しておられると思いますが、あなたたちに辛い思いをさせているのは、私ども夫婦の勝手な事情です。晴彦さんと真知子に悲しい思いをさせて本当に申し訳ないと思っています。薄情な親だということも分かっています。
今日は、晴彦さんにお詫びに来たのです。真知子にも断って来ました。真知子は何も言いませんでしたが、あなたに申し訳ないと伝えて欲しいと願っているのが親の私には分かりました。
正直に言えば、私も晴彦さんと真知子が結ばれるのを楽しみにしていました。真知子の伴侶に晴彦さんは相応しい方だと喜んでいました。
私の力が及ばなく、こういう結果になってしまい、晴彦さんと真知子には本当に申し訳なく思っています。親の都合で二人に悲しい思いをさせておきながら、私がこんなことを言うのはどうかとも思いますが、真知子はあなたを心から慕っています。真知子は苦しんでいます。どうか真知子を責めないでください。そして、どうか、真知子とのことは運命だと思い、忘れてください。私たち夫婦をいくら恨んで頂いても覚悟しております」
私は、ただ静かに聞いていた。真知子さんのお母さんも本当は私たちの味方なのだ。だが、なぜ私たちの未来を奪おうとしているのだろう?真知子さんのお母さんの頬には大きな涙が溢れている。
「ここでお別れさせていただきます。今までありがとうございました。真知子さんに、くれぐれも宜しくお伝えください」
私は、そう言って車から降りた。真知子さんのお母さんは心配そうに、お家の近くまで送らせてと言ったけれど、私は大丈夫ですからと断り、あてもなく歩き出した。
それから数日後、私は東京の伊藤へ電話した。伊藤は、真知子さんとのことは諦めたのかと確認した。そうだと伝えると、間違いなく採用されるよう頑張るから吉報を待てと言って電話を切った。直ぐにでも行動に移す気配がした。
私は、真知子さんと別れた後の北海道には何の未練もない。だが私は長男なので、上磯に住む両親と妹の許しが必要だった。最近の私のやつれた表情から、家族は私の東京行きを認めてくれた。次の日の朝、台所にいた妹に、迷惑をかけて申し訳ないと頭を下げると、妹は両親に聞こえないように小さな声で私に言った。
「お兄ちゃん、家のことは心配しなくて大丈夫!私が結婚しようとしている人は、次男だから、きっと養子に来てくれる!両親のことは、私がちゃんと面倒見るから心配しないで!」
こんなに妹が頼もしいと思ったことはない。涙もろい私は、瞼を熱くした。
数日後伊藤から、もし問題があれば伊藤が全責任を負うという条件で採用が決まったとの連絡が入った。私は伊藤に感謝しつつ東京行きを決心した。翌日私は、12月末日をもって退職との辞表を技師長に出した。技師長は、驚いたようだったが、私の再就職先の病院名を聞くと納得してくれただけでなく、むしろ応援してくれた。
伊藤の話では、年明け早々からの勤務となるらしい。私は、12月28日の青函連絡船の切符を購入した。少しでも早く函館を離れたかった。
師走は慌ただしい。忙しい日々であっという間に今年も残すところ僅かとなった。私は各部署に退職の挨拶回りをし、翌日から有給休暇を取った。
真知子さんには、どうしても見送りに来て欲しかった。最後の別れをしたかった。だが、直接真知子さんに伝えることを私は躊躇した。真知子さんが働いている時間帯に、具体的には平日のお昼頃に真知子さんの家に電話をした。期待した通り、真知子さんのお母さんが受話器を取ってくれた。
私が、北海道から離れ内地に行くことになった旨を伝えると、真知子さんのお母さんは急に涙声になり、いつ北海道を発つのかと聞いた。
「明後日の午前11時発の青函連絡船で東京に行きます。新年から、またレントゲン技師として東京のある病院で働くことになりました。もし、出来ましたら真知子さんに伝えて頂けたらと思いまして」
この声を聞くのも最後だと思った私は、蚊が泣くような小さな声で呟いた。
「真知子さんのお母さん、色々お世話になりました。どうか、いつまでもお元気で・・・」
最後の方は声にならなかったが、電話を切ると、もう終わったという思いが体中を駆け抜け、男のくせにまた涙を流した。
いよいよ内地への出発の朝、私は家族からの見送りを再度断り、青函連絡船の乗り場にひとり向かった。年の暮れの函館港は混雑していた。
私が青函連絡船の乗り場近くを歩いていると、紺のオーバーコートを着て、ハンドバックと茶色の紙バックを持ち、辺りを誰か探す素振りで立っている真知子さんが目に入った。私は走って駆け寄った。
「来てくれたの?ありがとう!」
私は真知子さんの瞳を見つめて言った。出航までにはまだ随分、時間が残されている。なるべく人混みを避け、私と真知子さんは隅の方に置かれたベンチに座った。私も、大きな荷物を両手に下げているので、今回はハンカチを真知子さんに敷いてあげることはできなかった。
人の目を気にする余裕は、今の私たちには無かった。私は、住所を書いたメモ用紙を真知子さんの手に握らせた。いきなり、真知子さんが人目も憚らず私に抱き付いてきた。私も、堪えきれなくなり涙を流した。
話すことはたくさんある筈だった。お互いを慰め合う時間も十分あった筈だった。だが二人は何も言えず、抱き合っていた。暫くそうしていた。ふと真知子さんは体を起こし、嗚咽を堪え、心の底から絞り出すような声で私に言った。
「晴彦さん、ごめんなさい。私を許してください。東京へ行ったら頑張ってね。素敵な人がいたら、私のことは忘れてい・・・・」
最後は聞き取れなかったが、真知子さんの言いたいことは私には分かった。真知子さんは、ふと思い出したように茶色の紙バックから何やら取り出した。
「私の編んだ手袋とマフラー、冬の東京も寒いでしょ?風邪引かないでね。それに、今朝作ったサンドイッチ、船の中で食べてね」
青函連絡船は私たちに少しの気遣いもみせずに、無情にも汽笛を鳴らした。私は、真知子さんに話す最後の言葉を考えて来たが、そんなことは忘れていた。
「真知子さん、一生忘れないよ。いつかまた函館で会うことがあった時は、笑顔で挨拶しようね」
私の差し出した右手の甲に、真知子さんの涙が落ちた。私は桟橋を真っすぐ進み、連絡船に乗り込んだ。振り返るのが怖くて、後ろを見なかった。
いよいよ出航という時、真知子さんは立ち上がり白いハンカチを振った。残酷な時の流れだった。白い航跡波の長さと真知子さんの姿が反比例して、いよいよ姿が見えなくなってきた。それでも、真知子さんの降るハンカチが左右にゆれているのが微かに分かった。
「もう、いいよ~。真知子さん、ありがとう!さようなら~」
周囲の客の存在も目に入らず私は大声で叫んだ。その時、霞んだ視野の先で揺れていた白いハンカチがいきなり私の視界から消えた。 つづく