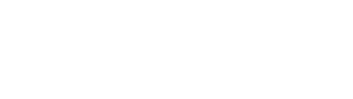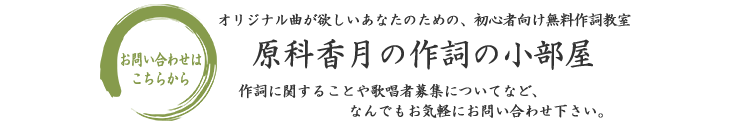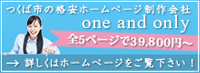課題テーマに挑戦「銚子港」第22回
2024年01月01日
 課題テーマに挑戦「銚子港」第22回
課題テーマに挑戦「銚子港」第22回
皆さま、新年明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い申し上げます。今年こそ、戦争のない誰もが安心して生きられる年となりますようにと祈ります。
お正月と言えば、お節料理やお雑煮です。元旦の朝をごゆっくりお楽しみくださいませ。
画像は、我が家のお節料理ではありませんが豪華です。
お雑煮も関西の方では丸いお餅のようですが、つくばのお雑煮は四角い餅です。
どうか、皆さま方が健やかで幸多い一年となりますように。
物語 想い出の銚子電鉄外川駅(第15話)
【その後の由香里さん】
由香里さんが家族と共に、東京から萩へと越してから、数日後に2年目となる正月を迎えようとしていた。
いつものように由香里さんが燃えるごみを出そうとして社宅の入り口を出ると、ちょうど出し終えたばかりの佐藤さんと出会った。
佐藤さんのご主人は、やはり東京から転勤になり、佐藤さんはご主人と二人暮らしをしている。萩に来て半年も過ぎた頃に、やはり燃えるごみ置き場で挨拶をするようになり、それから親しくなった。少し白髪が気になり始めた五十代半ばの優しい奥様だ。
「由香里ちゃん、暮れはいつからお休みになるの?」
初めの頃は「由香里さん」と呼んでくれていたが、今では「由香里ちゃん」と呼んで、気さくに接してくれる。萩で親しくなった初めての人だ。
由香里さんは、東京から越して来た翌月半ばから働き始めていた。
「あっ 佐藤さん。お早うございます。私、年末年始のお休みは明後日の29日からになります。今日あたりから、お節料理やお雑煮の準備をしようかと思っています」
由香里さんがそう返事をすると、佐藤さんが言った。
「由香里ちゃんは、お若いのに何でも頑張るのね。私たち夫婦には子供がいないから、何だか由香里ちゃんが自分の子供のような気がするわ。
ところで、お雑煮はどうするの?東京では四角に切った餅を焼いてすまし汁に入れたり、レンジで柔らかくしてから入れたりするけど、萩は違うのよ。私も初めは戸惑ったの。良かったら明日か明後日に、私のところに来ない?」
もう何度もお邪魔している佐藤さん宅は、気兼ねのない、由香里さんにとって本当に居心地の良い、まるで母がいた頃の我が家のようだった。
「はい。明日の十時頃なら大丈夫です」
由香里さんが返事をすると、佐藤さんは満面の笑みで「じゃあね、明日ね。待っているわ」と言い社宅の中に姿を消した。
次の日は土曜日だった。約束の十時になり、私は佐藤さん宅のインターホンを押した。
直ぐドアが開いて、佐藤さんが笑顔で現れた。
「いらっしゃい。コーヒー、それともお紅茶?ここに座っててね」
由香里さんがソファーに腰を下ろすと、間もなくコーヒーが運ばれた。
「由香里ちゃん、中学生の時にお母さまが亡くなられたんだったわよね?随分これまで頑張って来たのね!」
佐藤さんは涙目になりながら、由香里さんの前に砂糖とミルクとを差し出してくれた。
「はい、でも父と弟とも協力し合いながら、何とか楽しく生きて来られました。時々は、東京のことを思い出し、つい懐かしくなり、北東の空を眺めては感傷に浸ることもありますが」
佐藤さんは、急に大粒の涙を流し、ハンカチで拭った。優しい人だ。
佐藤さんが由香里さんを呼んだ訳は、萩の元旦に食べるお雑煮の話をするためだったらしい。
私に紙と筆記具を用意してくれてから、レシピを話してくれた。要約すると、以下のとおりだ。萩では「かぶ雑煮」が、古くから受け継がれて来たとのこと。
1 人数分より少し多めの水に煮干しを入れ、弱火で10分煮、だしをとっておく。
2 かぶは大きくいちょう切りにし昆布、するめは千切りにしておく。
3 かぶとするめをだし汁に加え、材料が柔らかく煮えてからしょうゆで味をつける。
4 丸餅が柔らかくなるまで煮る。(おもちが溶けないよう、煮立たせない)
5 雑煮を椀に盛り、三ツ葉をあしらう。
(出典 cookpad)
去年の萩での初めての正月は、由香里さんの母が生前作ってくれていた関東の雑煮にした。だが、スーパーで四角く切った餅が見当たらず、丸い餅を焼いてからすまし汁に入れ、後から三つ葉を添えた。出汁には鶏肉を使った。
今年は去年とは違うお雑煮だ。萩のお雑煮なのだ。由香里さんはすっかり張り切った。
元旦の朝に、予め用意をしておいた具材を使い、佐藤さんから教えて貰ったメモを見ながら、「かぶ雑煮」を初めて作った。だが、火加減が悪かったのか、少しすまし汁が濁ってしまった。先ず、仏壇の母に供えた。
「由香里、今年は萩の『かぶ雑煮』か?美味しいよ!この年まで、一度も食べたことがなかった。何か新鮮な嬉しいお雑煮だよ。由香里、いつも家族のためにありがとう。今年もよろしく頼むね」
元旦だというのに、父の目は潤んでいた。弟は何も言わなかった。中学生だ。思春期の真っただ中にいる。言葉はなくても、私には弟の気持ちは伝わっている。
私の第二の故郷萩のお雑煮を初めて作り、そして食べることが出来た。これは全て佐藤さんのお陰だ。佐藤さんの顔が亡くなった母の面影に重なった。
父が、ふと箸を持つ手を止めて言った。
「由香里、かぶ雑煮のお椀が一つ余っているけど、どういう訳だ?」
かぶ雑煮のお椀が食卓の上に一つ余計に置かれているのを、父は訝しがった。
「お餅を入れすぎちゃったから、お父さんか陽斗が食べてくれるかなと思って」
由香里さんは、お餅が多すぎたからと「かぶ雑煮」を余計に用意したのではなかった。本当は、萩で初めて食べる元旦のかぶ雑煮を、遥か遠い東京の翔ちゃんにも食べて欲しかったのだ。それも、同じ食卓で由香里さんの家族と一緒に。
亡くなった母までが応援してくれた翔ちゃん。由香里さんの翔ちゃんへの想いは、東京が遥か遠くになろうとも、その気持ちにいささかも揺るぐことはなかった。
萩での会社には自転車で行く。まだ、車の免許は持ってはいない。だが、勤務する会社までは自転車で充分だ。
由香里さんも東京にいる頃から、もちろん萩のことは知っていた。幕末から維新にかけて、萩は日本の国に重要な働きをした人物を数多く輩出した。吉田松陰・高杉晋作・桂小五郎・久坂玄瑞など枚挙に暇がない。テレビの大河ドラマでも見たことがある。
市内を流れる阿武川は、橋本川と松本川とに分かれて日本海へと注がれる。その中州に萩の観光名所が集中している。だが、吉田松陰を祀ってある松陰神社は中州から東に向かい山陽本線のガード下を通り越した先にある。
由香里さん親子が住んでいる社宅は、松陰神社が比較的近いところにあった。由香里さんは、会社の帰りがけや、休日の息抜きに良くこの神社を訪れた。その度に、拝殿で心の中で願うことがある。
「宮内さんが健康でご活躍できますように。もし出来ましたら、いつかまた宮内さんと会える日が来ますように。私と母の願いが叶いますように!」
由香里さんはある日の参拝の折、ふと思い付いたことがあった。
それは、毎月一度、宮内不動産に電話をし、社員の方の近況を聞くことだった。もちろん、翔ちゃんの様子を知ることが目的だ。健康でいるか?もしかしたら親しくしている異性の人はいないか?
だが、電話一つで翔ちゃんの全てのことが分かるとは到底思えない。だが、宮内不動産との縁を切らずにいたかった。翔ちゃんとの糸は、その赤い糸は、この電話でしか繋ぐことが出来ないのだ。
由香里さんは、このアイデアが決してベストとは思っていない。だが、翔ちゃんを諦めきれない今、これからも決して他の異性に想いを寄せること等考えられない今、出来うる限りの最善の方法だと、そう信じることにした。
正月休みも終わり、また忙しい日常が始まった。由香里さんは、朝の六時には起きて、朝ご飯の用意をする。三人での食事が済むと食器を洗い、薄化粧をし、着替えて8時には自転車で会社へと向かう。
由香里さんの会社は、工業用、土木用の機材や建材の卸売を手掛けている。従業員数100人に満たない中小企業だ。会社では、営業社員から依頼された見積書の作成などが主な仕事だ。だが、顧客等へお茶を出すことも仕事の内だ。
萩は、標高700mを超える山々が連なっており、大半が山地で占められている。低地は、阿武川河口で橋本川と松本川に別れたその三角州にある市街地と、その周辺に見られる。市街地周辺は観光地としては有名だが、第一次産業の就業者が多い。農林水産業地域として県下でも位置づけられている。市街地から離れた地域は、道が狭く、交通の便も悪い。
萩のこの地形が、大企業の進出を阻んでおり、地元の企業で殆んど占められている。
現在の日本は、異常な速さで人口の高齢化が進んでいる。決して萩も例外でなく、いや萩市においては全国平均を上回って進んでいる。人口減少、そして少子高齢化、萩市は厳しい現実の中でその対策を模索し続けている。
人口は毎年数パーセントの減少が避けられず、高齢化世帯も当然増えている。この対策として、当然萩市以外の他市町、もっと言えば県外からの比較的若い居住者を招き入れる必要がある。特に若い世代の第三次産業への就業率を向上させたい。それが未来の明暗を分ける。
由香里さんの父の会社のように、萩に進出する上場企業はまずない。だが、以上の問題を少しでも改善しようとする萩市の強い要望で誘致が決定された。企業側にも採算が全く無い訳ではなかった。
萩に支社を設立したての頃の経営状況は、決して悪くはなかった。行政及び住民からの熱烈な支援があったからだ。だが、この日本全体が経済が灰色の分厚い雲に覆われ、上向きの未来が見えない中、萩の支社も次第に経営状況に影を落とした。故に大幅な営業改善という本社の強い意向を全うするため、由香里さんの父は転勤となり赴任したのだった。
由香里さんは、自転車での通勤は特に不便を感じていない。だが、バスの便があまり良くない。スーパーや洋品店への自転車での買い物には数十分もかかる。父と相談し、車の免許を取ることにした。もちろん父も車の免許は持っていない。だが、家族で出かけたり、家事をするためには必要だと理解してくれた。
自動車教習所は、萩藩の人材育成の中枢を担い、多くの先覚の士を育てた藩校明倫館の近くにあった。だが、教習所の営業時間は夕方の5時までだ。困った由香里さんが父に相談すると、事情を会社に話して見たらとの助言だった。
翌日の昼休みの時、上司の片岡係長に相談すると、笑顔での返事が返って来た。
「渋谷さん、確かにこの萩では車がないと不便だよね。会社でも、渋谷さんに銀行やお客様の所に行って貰うことがこの先どうしても出てくると思うので、課長に夕方にでも話してみるよ」
その言葉通りに、翌日の朝、片岡係長から話があった。内容は、課長から部長に話が伝えられ、午後3時から教習所に通うことが許可されたとのこと。由香里さんが喜んだのは当然だった。だが、それだけではない。その時間を勤務扱いにするという会社側からの計らいもあった。
それから、平日は午後3時に帰らせて貰い、自動車教習所に向かった。同僚社員からは、特に羨望の眼差しを向けられることはなかった。前にも、前例があるからだ。
そして、由香里さんの自動車教習所通いが始まった。会社から真っすぐ自動車教習所に向かったがそれでも30分はゆうに超えた。
由香里さんは、殆んど自家用車に乗った覚えがない。それは、東京では車は特に必要が無かったからだ。バス停に立つと数分でバスが次々にやって来る。電車もそうだ。
教習所に入校すると、教室で学ぶ学科教習、そして構内の路上で車に乗る技能教習を受講することになる。初めて技能教習を受けた時のことだ。
教習指導員の指示で初めて運転席に座った。ハンドルを握るのも初めてだ。この私が運転免許証を取れるのかと、由香里さんは不安に思った。
「渋谷さん、運転席に座るのは初めてですか?心配は要りません。去年でしたか60代の方が初めて教習所に来られた例があります。他の方よりはもちろん、時間が掛かりましたが、もちろん合格されて、今ではどこに行くにも車を利用していて、他の市町の名所めぐりまでされているそうです。渋谷さんは若いのですから、直ぐ取得出来ますよ」
由香里さんは、この既に還暦を過ぎたであろうと思われる指導員の優しさに、ホッとして微笑んだ。
教室で学ぶ学科教習は、普段忙しい由香里さんには時々眠気が襲う。だが、今は仕事中なのだと自分に言い聞かせ、何とか頑張っている。
ある日、いつもの教室で「安全運転の知識」のビデオを見ていて、人の視線に気付いた。最近、ふと誰かの視線を感じることが時々あった。気のせいだと思っていたが、確かに誰かが私を見ている。その感じる視線に目を向けると、同年代と思われる若い男性だった。
「あれ!宮内さんに似ている」
瞬間、そう思った!確かに翔ちゃんに似ている。どこがかというと、上手く説明が出来ないのだが、髪型から顔の輪郭、そして二重の眼と眉毛の辺りも確かに似ている。
その時から、由香里さんはその男性が気になった。
その夜、翌日の炊飯の用意も済み、お風呂にも入り、やっと布団に横になったのだが、どうにも気になって仕方がなかった。あの若い男性は何故私を見つめていたのか?それにしても、宮内さんに似ていた。この世には、自分とそっくりの人間が3人存在すると誰かが言っていた気がする。
高校生の頃だったか通学の帰りの電車の中で、反対側の正面に座った中年の女性が、隣の娘かと思われる少女に話しかけていたことがあった。小声だったが、良く聞こえた。
「麻美、正面の高校生、府中の従妹の小百合ちゃんにそっくりだと思わない?」
少女も頷き、そして興奮して言った。
「本当ね!まるで小百合ちゃんが座っているみたい。信じられない!」
由香里さんは特に反応はしなかった。小百合さんという人を私は知らないし、興味もなかった。だが、今回は違う。なぜなら、由香里さんが心から恋しく思っている人、宮内さんにそっくりな人なのだから。その夜はなかなか寝付かれなかった。
それから由香里さんは、あの男性が妙に気になって仕方がなかった。自動車教習所の中では、時々見かけることがある。由香里さんに気付くと、その男性は軽く会釈をしてくれる。何かはにかんでいるようだ。由香里さんは、どう対応していいのか分からなくて、曖昧に会釈をする。やはり何度見ても、宮内さんに似ている。
ある日、途中用を済ませ、遅れて自動車教習所に着いた由香里さんは入り口に走った。急いでドアを開けた。その時だった。入り口から出てきた男の人と接触し、由香里さんは体制を崩して地面に両手を着いた。
「大丈夫ですか?ごめんなさい」
立ち上がった由香里さんに、そう言って頭を下げた男性は、宮内さんに似ているあの青年だった。由香里さんは、この偶然に戸惑いながら言葉を発した。
「いいえ、私の方が悪いんです。遅れて来たものですから、走って来ていきなりドアを開けて」
由香里さんが頭を下げると、その青年が言った。
「あのう~。小学6年生の時、椿東小学校から確か大分の方に転向された田村和子さんじゃないですか?」
その青年は、由香里さんを誰かと勘違いしていたようだった。
「私は東京から越してきた者です。地元の小学校には行ったことがありません」
そう言うと、青年は頭を搔きながら恥ずかしそうに言った。
「そうでしたか?私の勘違いでした。申し訳ありません。私は、その田村和子さんに好意を持っていたものですから、つい、もしかしたらなんて思ってしまいました。恥ずかしいです」
由香里さんは、「それでは」と言って、建物の中に急いだ。
その夜もまた、遅くに布団に入った由香里さんは思った。何という偶然だろうか?私が憧れていた宮内さんに似た男性が、私に似た小学校時代の女性に想いを馳せていたとは!
由香里さんは、何か妙に因縁めいたものを感じたが、そこで考えるのをやめた。
「宮内さんに似た人がいたから、その人で我慢しようなどと思うことは、宮内さんを心から慕っていないということなんだわ。不謹慎なことだわ。もう、忘れることにする」
由香里さんは、そう言い聞かせながら眠りに就いた。だが、由香里さんの意思とは違い、あの青年と間もなくデートすることになるとは夢にも思わなかった。 つづく