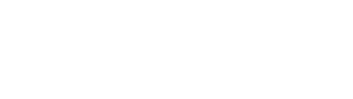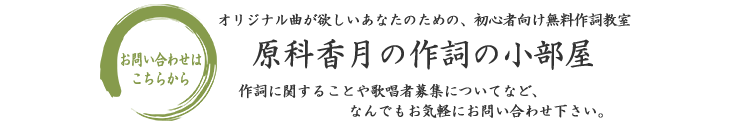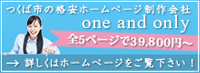創作の小部屋「鳥海山物語」
2018年01月14日
 創作の小部屋「鳥海山物語」
創作の小部屋「鳥海山物語」
この物語は、「鳥海山をテーマにした作詞をして欲しい」との秋田県のアップルスターさんのご希望で、作詞の基となるお話をまず作り、その後から作詞作業に入る予定で書き始めました。
少し長すぎましたが、どうぞ最後までお読み下さいますようお願いいたします。この物語から生まれた「鳥海山物語」の歌唱は、トップページ「私が作詞した曲」からご視聴頂けます。
鳥海山物語
第1章 (第1回目) 昭和36年頃
昭和30年代のお話です。
鳥海山の麓に、暮らしの貧しい母と子が住んでいました。
母の名をふみ子と言いました。子供の名前は由美子です。
ふみ子の亭主は、娘の由美子が3歳の時に、急な病で亡くなりました。
幼い子との生活のため近くの工場の下働きをし、朝から晩まで埃だらけの姿でなりふり構わず働きました。幼い由美子が一人で過ごす時間も多くなりましたが、ふみ子は一緒のときは由美子に十分な愛情を注ぎました。
やがて由美子は小学生になりましたが、暮らし向きは変わりませんでした。
お世辞にもきれいな身なりとは言えない姿で、母が仕事で一人の時は、いつも庭に出て鳥海山を眺めていました。由美子の家からは、鳥海山が良く見えました。不思議なことに鳥海山を眺めていると、寂しさを感じなかったのです。
小学4年生の時でした。隣の席の女の子の消しゴムが無くなり、由美子が疑われたことがありました。その消しゴムは当時流行りのとてもきれいな色をした、級友の誰もが憧れていたものでした。由美子は言い訳もせずに、机に顔をうずめて泣いていました。
家に帰っても由美子は悔しくて泣きつづけました。心配したふみ子が訳を聞くと、やっと重い口を開いて訳を話しました。
「由美子、盗っていなければ泣くことはない。神様がちゃんと見ていて下さるから、安心して学校に行きな。だいじょうぶ!」
次の日、教室に入った由美子にたいし、級友たちは「泥棒~由美子! 貧乏~由美子!」とはやし立てました。今度は、由美子は泣きませんでした。母を信じていたからです。でも話し相手もなく、ひとり海苔の佃煮の弁当を食べ、ひとりで下校しました。
途中、田んぼ道の脇に大きな石があり、母が仕事で遅くなる時はいつもその石に座り、鳥海山を眺めて過ごすのでした。今日は、由美子は涙を流しながら、鳥海山に話しかけました。
「私、なにも悪いことなんかしていないのに、なんでみんな苛めるの!」
ここでは誰にも邪魔をされることはありません。由美子は涙に濡れた顔で鳥海山を見つめました。菜の花越しの鳥海山は雪で覆われ、幼い時に亡くなったので記憶は曖昧だけれど、その雄大な姿は父親のように由美子には映りました。暫らく泣いていると、「由美子、もう泣くな!由美子をいつも見ているよ!」鳥海山の優しい声が聞こえて来たように由美子は感じました。
第1章 (第2回目) 昭和41年3月
母は、また同じことを言いました。
「由美子、盗っていなければ、もう少し我慢しろ。だいじょうぶだ!」
また次の日も級友は、同じように囃し立てました。
「泥棒~由美子! 貧乏~由美子!」
由美子は、泣かずに唇をかんで耐えました。担任の先生は、「もし、間違えて持って帰ったのなら、返してやってね。」と特に由美子を庇うこともありませんでした。
それから数日して、隣の女の子が由美子に謝りました。家の机の引き出しの奥から、あのきれいな色をした消しゴムが出てきたとのことでした。
由美子の無実は晴れても、級友たちは誰も由美子に詫びたりしませんでした。ただ、村一番のお金持ちの家の総一郎だけは、由美子に頭を下げました。
「由美子、悪かった!疑ったりして、本当にごめんな!」
総一郎は、クラスでトップの成績で学級委員を務めて、女の子の憧れの的でした。
母はなぜこの日が来ることが分かったのか、この時には由美子は不思議でなりませんでした。
月日が経って、由美子が中学を卒業する3月になりました。由美子の家は貧乏なので、もちろん上の学校に進むことはずっと前から諦めていました。進路相談の頃には、担任の先生が何度か家にやってきて、母のふみ子に由美子の進学を勧めましたが、母と子は首を縦に振ることはありませんでした。村の小さな縫製工場で働くことに決めていたのです。先生がわざわざ訪問したのは、由美子の成績がとても良かったからです。
4月になって、あの総一郎から手紙が届きました。直接ではなかったけれど、総一郎と仲の良い近所に住む男の子が、「総一郎から頼まれた。」とだけ告げて、手紙を差しだしたのでした。鳥海山の頂きは、まだ真っ白い雪に覆われていました。
第1章(3回目) 昭和43年夏
「由美子ちゃん、僕は学校が遠いので寮に入ります。ここには、夏休みには、帰ってきます。その時は、もし出来たら会いたいです。どうか元気で、お仕事頑張ってください。」
ただそれだけの短い手紙でしたが、由美子はとても恥ずかしい気持ちと、嬉しい気持ちが重なり、胸が高鳴るのを抑え切れませんでした。
ヒマワリのつぼみが膨らみ、蝉が甲高い声で鳴き始めました。そうです。夏がやって来たのです。でも最近の由美子は、縫製工場での仕事中も何か考え込んでいる様子です。同じ中学から入った美代子が心配して、お昼休みにこっそり尋ねました。
「由美ちゃん、何か心配事?なんか変だよ!」
由美子は、「何でもないよ、有り難う」と返事をしましたが、また考え込んでいる様子でした。
いつか総一郎からの手紙を届けてくれた、近所の男がまた現れました。総一郎からの手紙を届けに来たのです。
「由美ちゃん、昨日実家に帰りました。元気でしたか?明後日、日曜日なので、御嶽神社で会いませんか?10時に鳥居のところで待っています。」
やはり短い手紙でしたが、由美子には総一郎の気持ちが伝わってきました。ですが、由美子の表情はなぜか雲っていました。
由美子は母が縫ってくれた浴衣を着て御嶽神社に向いました。由美子は正直に、同級生の総一郎に会いに行くことを母のふみ子に伝えたので、古い小さな箪笥から「お祭りの時に恥ずかしくないように!」と予め縫って置いた浴衣を取り出し、着せてくれたのでした。
鎮守の森に囲まれた神社の鳥居に着くと総一郎が待っていました。総一郎はだいぶ前から待っていたらしく、顔を紅潮させて嬉しそうに言いました。
「由美ちゃん、来てくれてありがとう!前に手紙を渡したのに、返事が貰えなかったので、今日は来てくれないかとずっと心配だったよ。」
「ごめんさない。手紙はとっても嬉しかった。私嬉しかった・・・」
やっと笑顔でそれだけ言うと、由美子の表情はまた曇ってしまいました。
由美子の表情の変化に気付いた総一郎が、由美子の顔を覗き込みながら言いました。
「由美ちゃん、どうしたの?なんでそんな悲しそうな顔をするの?」
鳥居をくぐり、境内を入ると本殿です。総一郎が言いました。
「由美ちゃん、先ずお参りしようよ。」
二人は、静かにお参りしました。由美子は両手を合わせ、ずっと長いこと頭を下げて、何かをお祈りしていました。
境内を歩きながら、いつか二人は手をつないでいました。
「由美ちゃん、これから僕と付き合って欲しんだけど、いい?」
総一郎の言葉に、はっと我に返ったように、由美子はつながれた手を解きました。
「私、とても総一郎さんとお付き合いは出来ない・・・。」
第1章(4回目) 昭和43年夏
「私、とても総一郎さんとお付き合いは出来ない・・・。」
そう言って、由美子は急に涙を流しました。由美子の突然変わった態度に、総一郎は驚き、そして訳を尋ねました。
「どうしたの?由美ちゃん、なぜ泣いているの?」
由美子は、小さくしゃくり上げ泣いています。総一郎は、どうしたものかと思案しましたが、訳を聞かずにはおられませんでした。
「さっき、手紙が嬉しかったと言ったばかりじゃないか?」
由美子の顔を覗き込むように総一郎は、優しく聞きました。
しばらく泣いていた由美子でしたが、もう観念したかのように聞き取れない程の小さな声で、涙を拭きながら話し出しました。
「ごめんなさい。訳も言わず泣いたりして!私にはお父さんがいないし、とても貧乏だし・・お、お母さんが・・・総一郎さんとは・・付き合うなって!・・」
総一郎にもやっと由美子の涙の訳が理解できたのでした。
由美子の母は、富豪の家の長男の総一郎と父親のいない貧しい由美子が、将来結ばれることは決してあり得ないと信じているのである。当人同士が良くても、総一郎の親やその親戚の者が反対するに違いない。その時になって、由美子に辛い想いをさせるより、初めから諦めさせた方がどれ程由美子のためだろう。そう思っている。
総一郎にも、由美子の母の心が痛いほど分かりました。由美子の心を思うと、総一郎は由美子が不憫になり、また尚一層愛おしくなり、その小さな肩を抱きしめたい衝動に駆られました。
「由美ちゃん、もう泣かないで!大丈夫、僕がきっと守って見せる!」
由美子の瞳はますます潤み、由美子もまた総一郎の胸に飛び込みたい衝動に駆られていました。
二人は、また手をつなぎ境内を歩き始めました。由美子の表情は先程までとは打って変わり、杜の間からの木漏れ日を浴びたその横顔は、とても美しく輝いていました。
第2章(1回目) 昭和46年1月
月日は流れ、由美子はもう直ぐ成人式を迎えていました。町の小さな縫製工場も、景気が良くなって来たためか、由美子の毎月の給与も少しずつだけれどが良くなってきています。ですが、由美子は自分の物を買うことは慎しみました。母にそっくり給与袋を渡し、その中から小遣いを貰ってやり繰りしています。
由美子はずっと以前から、その小遣いを節約し預金をしていました。
あの日、十五の春の御嶽神社のことは母に話していませんでした。母のふみ子は、由美子が総一郎とは既に別れたものだと思っているに違いありません。それは由美子が母の言うことに逆らったことが無かったからです。
成人式には、また総一郎が帰って来ます。華やかな場所で二人だけで話をすることは出来ないので、やはり成人式の前後の日に御嶽神社で逢うことになるだろうと由美子は心待ちにしていました。
毎月の小遣いの中からの預金は、総一郎に暖かいマフラーと綿の手袋を買うためのものでした。そのためには、欲しかったネックレスやブローチも諦めました。
成人式の2日前、いつもの同級生の男がまた総一郎の手紙を母のいない時間を見計らって届けに来ました。由美子の予想した通り、御嶽神社で逢いたいとのことでした。成人式の次の日を指定していたけれど、由美子に問題はありませんでした。
御嶽神社で逢ってからは、総一郎とは正月とやはり夏休みの8月に何度か逢っていました。時々は境内で人を見かけることはありましたが、高齢の人ばかりで、とりたてて二人を注視する者はおりませんでした。
その総一郎は既に大学生になっており、東京の大学の近くにアパートを借りて学業に専念していました。遠い首都東京に、由美子も憧れの気持ちは少なからずあったことは事実です。
ですが、今回の御嶽神社での逢瀬に悲しい出来事が待っていることに、由美子は嬉しさばかりで気付くはずもありませんでした。
第2章(2回目) 昭和46年1月
成人式には、由美子は出席しませんでした。ずっと以前母が縫ってくれた着物には愛着はありましたが、成人式の晴れの舞台には相応しい着物ではなかったのです。
由美子は、御嶽神社を今日ほど遠くに感じたことはありませんでした。由美子は足早に歩きました。いつもは平気なのに、息切れがし、そして喉が渇きました。やっと鳥居に着くと、既に総一郎は着いていて、顔を真っ赤にして喜びました。
「走ってきたの?息が辛そうだね。これを飲んでごらん。」
総一郎は小さなカバンの中から缶ジュースを取り出し、由美子に差し出しました。みかんジュースでした。少し缶の匂いがしたけれど、乾いた喉にはとても甘くて美味しい飲み物でした。
「おいしい!甘くて美味しいね~!」
由美子は、総一郎に開けてもらった缶ジュースに喉を鳴らしました。傍で総一郎がさも嬉しそうに、笑顔でその様子を見つめています。
「由美ちゃん、なんで成人式来なかったの?」
総一郎に聞かれて由美子は困ったが、本当のことが言えず母の用事があったからと言い訳をしました。
「由美ちゃん、僕、大学を卒業したら東京の会社に入って働くつもりなんだ。大きな会社なんだよ。先輩が大勢いて、僕にも卒業したら来いよって、言ってくれてるんだ。僕、長男だけど親父もお袋も、一度の人生だからお前の好きなようにしたらって。」
由美子は眩暈がしました。
確かに総一郎は長男だけど、弟が二人もいるのです。弟たちは地元に残るらしい話に、由美子はいっぺんに悲しくなってしまいました。由美子には、3歳で父に死なれてから夢中で働き、自分を育ててくれた母がいるのです。
母を、一人にはできない・・・!
総一郎と、将来を約束した訳ではないけれど、由美子の小さな胸が震えるほどの衝撃の中で、由美子はその瞬間母を想いました。
第2章(3回目) 昭和46年1月
「由美ちゃん、どうしたの?また、悲しそうな顔をして。」
由美子は、言葉が出て来ませんでした。ただ潤んだ瞳で総一郎を見つめました。由美子は、心の内を察して欲しいと思ったのです。
中学校を卒業した年の夏、帰省した総一郎と初めてこの神社で逢ったそのとき、総一郎と逢うことを母に反対されたと伝えた折、総一郎は由美子を守って見せると確かに言いました。
今の由美子にとって、自分を守ってくれるということは、同時に母も切り離しては考えられないことでした。それを、総一郎は分かってくれているのだろうか?しかし、それは言えませんでした。総一郎に負担を掛けるだけであり、総一郎の両親や親せきからの反発を増長させるだけになるに違いないと思ったのです。
由美子が3歳の時に夫を亡くし、なりふり構わず働き、何とか由美子を育ててくれた母。その母に、寂しい想いまた辛い想いをさせることは、何としても避けなければならない、そう由美子は思っていました。母の今後の人生は、由美子が守らなければならない、日頃由美子はそう考えていました。
「由美ちゃん、どうしたの?僕は大学を卒業したら、東京の大きな会社に入って、由美ちゃんさえ良かったら、東京で一緒に暮らして欲しいんだ。」
それは、間違いなく総一郎からのプロポーズでした。
「私は、東京へは行けない・・・。」
由美子は、絞り出すように、自分に言い聞かせるように、ゆっくり小さな声で総一郎に言いました。
先程まで赤みが差して、いかにも健康そうなその総一郎の顔が曇りました。総一郎は、必ず由美子が喜んでくれると信じていました。きっと、頷いてくれると信じていました。
由美子は、手提げの紙袋を開け、中からマフラーと手袋を取り出し、総一郎に差し出しました。
「総一郎さん、これ使って頂戴ね。東京も冬は寒いでしょ?」
総一郎はまた急に笑顔になり、マフラーを首に巻き、手袋をはめました。曇った総一郎の顔がまた赤みをおびて、その整った顔が喜びに弾けました。
「由美ちゃん、暖かいよ。ありがとう。東京は秋田ほど寒くないけど、ビルの谷間の隙間風は、すごく冷たいんだ。」
嬉しそうな総一郎の言葉を聞き笑顔を見ると、由美子は微笑みました。そして、これまで欲しかった物も我慢した甲斐があったと、由美子は幸せな想いに一瞬浸ることが出来たのでした。
「総一郎さん、私、やっぱり総一郎さんとお付き合いは出来ない。ごめんなさい!」
由美子は、初めて御嶽神社で総一郎に逢い、涙を流した時と同じように、また涙を流しました。そして、「さようなら!」とだけ言うと、家に向かって走り出しました。
第2章(4回目) 昭和46年2月
走って家に辿りついた由美子は、裏の物置の陰で泣き続けました。総一郎が、後から大きな声で由美子の名前を呼び続けているのを振り切って、由美子は自分だけが我慢すればそれで良いのだと、ただそれだけでした。
御嶽神社から泣いて戻ってから一月後くらいに、総一郎からの手紙をまた同級生だった男が届けに来ました。総一郎は、直接由美子の家に送らず、この同級生の男に、届けてくれるよう頼んだのでした。
「由美ちゃん、あれから一月が経ちますが、僕にはどうして由美ちゃんが突然泣き始め、そして帰ってしまったのかが、いまだに分かりません。僕が、何か由美ちゃんに悪いことをしたのでしょうか?それだったら、許して貰えるまで詫び続けます。マフラーと手袋は、毎日使っています。とても暖かくて、由美ちゃんと一緒にいるようです。もう直ぐ春休みです。お願いですから、また御嶽神社で会ってください。」
由美子は、手紙を読むとまた悲しくなり、また物置に入り咽び泣くのでした。
やがて再び春がやって来ようとしています。総一郎はきっと近く帰って来るだろうと思うと、胸が張り裂けそうな辛さを感じずにはおれませんでした。
総一郎の誘いを断ろうか、でも会いたい!由美子は、悲嘆にくれるのでした。
由美子が縫製工場からの帰り道、鳥海山が真正面に見えるいつもの田んぼ道の岩に腰を降ろし、うつむいて考え事をしているといきなり母の声がしました。
「由美子、どうしたんだ?何を考え込んでいる?」
母の声に驚いて、由美子は一瞬たじろぎました。母は、やはり母です。由美子の気持ちをもう察しています。
「由美子、正直に話してみろ。隠さないで、話してみろ!」
母の声は、低く凛としていました。
第2章(5回目) 昭和46年3月
(この母に嘘は通じない。母を信じることだ。それしかない。)
由美子は、これまでのことを隠さずに話しました。ただ、別れようとはしているが、それは母のためだとは言いませんでした。
母は、由美子の目を覗き込むように、じっと由美子の話を聞いていました。
「分かったよ。由美子、由美子が好きなら、私は反対しない。だが、一つだけ言っておく。総一郎さんと一緒になるのは、きっと無理だと思う。総一郎さんがお前を好きでも、でも総一郎さんは、佐々木家の長男だ。昔からの立派な家柄だ。お前とは釣り合わない。親や親せきの人たちが反対するだろう。その時、お前が泣くことがあっても、その覚悟があれば私は反対しない!」
母のふみ子の目にうっすらと光るものがありました。(由美子は、この私のために別れようとしている。)
3月に入って間もなく、いつもの同級生が総一郎の手紙を届けに来ました。
「由美ちゃん、どうしても逢いたい。逢って話がしたい。だから明後日の10時に御嶽神社の鳥居で待っています。」
いつものように、短い言葉で要点だけが書かれていました。
今度は、由美子も心を決めました。
(母が許してくれた以上、もう自分の気持ちに逆らう必要はない。自分のこの思いを天に任せて、真っ直ぐ歩いて行こう。たとえ、泣くことになろうとも!)
由美子のこころから、今までのような弱々しさはすっかり消えていました。
総一郎から指定された時間に間に合うように、由美子は家を出ました。今度は、母に総一郎と会うことを話してあったので、母は予め赤く可愛いリボンを買って来てくれて、由美子の髪に結んでくれました。母の気持ちが嬉しくて、朝から涙目の由美子でした。
約束の御嶽神社に由美子は着きました。
第3章(1回目) 昭和49年1月
池には、赤や金色の錦鯉が優雅に泳いでいます。その池の近くを、何人かの使用人が忙しそうに行き来しています。ここは、総一郎の生家なのです。総一郎は、正月で帰省しました。
離れの八畳間で、世界史の本を読んでいる総一郎に、女中のお里が障子の向こう側から声を掛けました。
「総一郎さん、お父様がお呼びです。」
総一郎は、面倒そうに本を閉じて、父親の部屋に向いました。
父は着物姿で座卓に新聞を広げていましたが、何か考え事をしているように総一郎には感じられました。
「総一郎、ちょっと話がある。そこへ座れ。」
総一郎は、父と真向いの位置に腰を降ろしました。
「総一郎、もう直ぐ卒業だ。東京の北星産業への就職は良かった。この会社はこれから大いに伸びると思う。
ところで総一郎、仁賀保には私が昔からお世話になっている竹内義彦さんという人がいるんだが、おまえも何度か会ったことがあるから覚えているだろう。
竹内さんは、結構大きな電機部品を作る会社を経営しているんだが、お前のことを気に入っていて、北星産業で何年か働いた後に、竹内さんの会社に来て欲しいと言うんだ。さっきも言ったが、私が大変お世話になった方だから、私からもお前に頼む。ぜひ、そうしてやってくれ!」
総一郎は暫く考えさせてほしいと父に話して、俯きながら離れの部屋に戻りました。
部屋に戻ると座布団を枕に総一郎は横になり、父の本意を知ろうと思いを巡らせました。
いつだったか、確か中学3年生の頃に、両親が竹内義彦さんの話をしていたのを思い出しました。確か竹内さんには子供が一人で、それも娘さんらしく、跡取りのことで悩んでいるようだとか、そういう話だったように記憶していました。
父は、まだ本当のことを言うのを躊躇しているのだろう。総一郎に、竹内家の養子に入って欲しいと話すのは時期尚早と考えているに違いないと確信しました。
総一郎は由美子のことを想い、そう遠くない時期に自らの本心を父に話さなければならないと、総一郎は天井を見つめながら覚悟しました。
第3章(2回目) 昭和49年1月
父からの竹内さんの会社への転職を半ば懇願された総一郎に、もう3年前にもなる「赤いリボンを付けた由美子」との御嶽神社のあの日の記憶が鮮明に蘇ってきました。
母に赤い可愛いリボンを髪に結んで貰ったという由美子の顔は、若さが溢れとても眩しく総一郎には映りました。瞳は輝き、総一郎の少し赤みを帯びた頬を遠慮なくまじまじと平気で見つめています。その表情から、総一郎への信頼、いやすべてを総一郎に託すという由美子の強い決意が読み取れました。
「私、もう怖くない。じぶんに正直に生きたい。」
それは笑顔で馳せられたものでありましたが、その愛おしさに由美子を抱きしめたい衝動に再び総一郎は襲われました。ですが閑散とした神社ではあっても世間の目があり、自重せざるを得ませんでした。
「由美ちゃん、今日は随分と明るいね。赤いリボンが素敵だよ!由美ちゃんは笑顔方が可愛いよ。」
この御嶽神社で由美子は何度泣いたろう。今の由美子はすっかり明るく変わり、澄んだ心が手に取るように総一郎に映りました。この由美子を必ず守り通さなければならないと総一郎は決意を新たにしたのでした。
「総一郎さん、もう私泣かない。これからは、総一郎さんに絶対涙を見せない!」
もし、総一郎がもう一度東京で暮らそうと言ってくれたら、今度は断ることはしないと由美子は覚悟を決めていました。だが、この日の総一郎の口からは、その話は出ませんでした。二人は、手をつないで境内を歩き、途中椅子に腰かけ幸せなひと時を過ごしました。時間はあっという間に過ぎ、もう暮れの夕やみが迫って来ていています。
また、5月の連休に会う約束をして別れました。別れ際、由美子が不意に総一郎の胸に飛び込んで出来ました。
「私、嬉しい。早く5月になればいいのに!」総一郎の胸の中で、由美子は甘えるように言いました。総一郎は優しく肩を抱きながら、由美子の甘い髪の匂いに心が躍りました。
もう今年は由美子も総一郎も23歳になります。女の由美子は、既に適齢期となり、由美子の数少ない伯父や叔母から、見合いの話が舞い込んで来ているようで、母のふみ子が、「まだその気がないようで、私も困っている。だが、嫁に行かれると私も寂しいし、まあ、そう急がなくとも。」と適当にあしらってくれていると去年の夏休みに逢った時に聞いていました。
離れの八畳間で寝ころびながら、両親に由美子のことを話さなければと思いながら、総一郎はこれからのことを思うと少し気が滅入ったのは事実ですが、だが由美子との幸せを思い浮かべると決心は少しも揺るぐことはありませんでした。
明日は東京に帰る日と決めており、その前に両親に由美子との結婚について話そうと総一郎は覚悟しました。
第3章(3回目) 昭和49年1月
翌朝、両親と総一郎と二人の弟の5人で朝食を囲んだ折、総一郎は皆が食べ終わるのを待ち静かに父に向って言いました。
「お父さん、今日の夕方東京に帰るけど、その前に話したいことがあるんだ。お母さんも一緒に聞いて欲しんだけど。」
父と母は顔を見合わせて、不思議そうな顔をしました。
「いいけど、午後はちょっと用がある。朝飯が済んだら、おまえの離れの部屋に行く。」
総一郎は、少し散らかった雑誌やノート類を片付け、両親を待ちました。
暫くして二人の足音が聞こえてきました。
「入るぞ。」父の威厳に満ちた声がし、同時に襖が開きました。若い総一郎に覚悟は出来ていましたが、胸の鼓動が高鳴るのが分かりました。総一郎は、自分の想いを素直に話し、出来ることなら円満な承諾が欲しいと願っていました。
差しだした座布団に座った父は、母がまだ座りきらないうちに言葉を発しました。
「総一郎、何の話だ。お母さんまで呼びつけて。」
総一郎は、何から話そうかと迷いました。
「父さん、僕が北星産業で3~4年働いた後、竹内さんの会社に入ることは構わないよ。僕も、東京の一流会社で歯車として働くよりも、将来組織の中心として働ける、それ程大きくない会社で働きたいと思っていたんだ。」
父は、「そうかそうか。」と満足そうに頷きながら、笑顔になりました。
「じゃ、そのように頼むよ。話は、それだけだな?」
父が立ち上がろうとした瞬間、総一郎は土下座をしました。
「お父さん、お母さん。聞いて貰いたいことがあるんだ。」
総一郎の突然の土下座に何事かと母のしのぶは驚きましたが、一呼吸おいて総一郎の手を取って言いました。
「総一郎、親子なんだから土下座なんかしないでおくれ。遠慮せずに訳をはなしてごらん。」
「父さん、母さん、僕には好きな人がいるんだ。その人と一緒になると決めているんだ。だから、その人と一緒になるのを許して欲しいんだ。」
総一郎の真剣な瞳に、父も母も一瞬凍りついたように表情を失くしました。が、父はすばやく事の重大さに気付き、顔を紅潮させました。
「総一郎、お前に好きな人がいても、その人と一緒になることは許せない!」
先程の笑顔も消えて、命令するかのように厳しく言いました。
「まあ、お父さん。いきなり決めつけては総一郎が可哀そうではありませんか?」
父に母は諭すように言い、今度は総一郎に向って言いました。
「総一郎、お前の好きな人はどこの誰なんだい?大学で知り合った人なのかい?」
総一郎は、畳を見つめたままの顔を上げ、父に向って言いました。
「小学校からの同級生の、村上由美子なんだ。いま、阿部縫製工場で働いている。出来れば、今年の秋には一緒になりたいと思ってるんだ。」
「お前、村上由美子って、ご亭主に先立たれたあのふみ子さんの娘さんかい?」
母の顔はまるで血の気を失くしたように、ただ唖然としていました。そして父もまた同じでした。
第3章(4回目) 昭和50年8月
御嶽神社にも蝉の鳴き声が響く季節になりました。鳥海山を囲む山並みは、緑が映えてとても美しい風景です。
ふみ子が工場の隅の汚れた休憩室で、麦飯のおにぎりと沢庵でお昼を食べていると、隣に座った同じ下働きのおみねが煤けた急須から湯呑にお茶を注ぎながら話しかけてきました。
「佐々木御殿の長男が、仁賀保にある大きな会社の社長の家に婿入りするって、もっぱらの噂だよ。」
ふみ子は、何の話か一瞬耳を疑いました。あの総一郎が、まさかそういう事態になる筈がない。何かの間違いにちがいないと、ふみ子は何度も心の中で繰り返しました。
「何でも、相手の社長さんには佐々木御殿のご主人が随分と世話になったらしく、一人娘の婿にと頭を下げられたという話だよ。確か息子さんの名前は総一郎さんとか言ったような気がするけど。」
ふみ子は、やはり反対しておけば良かったと思いました。辛い別れをすることは初めから分かっていたのにとふみ子は自分を責め、体中から血の気が引くのを感じました。
おみねは、ふみ子の様子が急に変わったのにも気づかず、おにぎりを頬張りながら瓜の漬物をしきりに勧めました。
「ふみちゃん、そう言えば由美子ちゃんもすっかり綺麗になって、誰か好きな人でもいるんじゃないの?」
仕事を終えて家に帰ったふみ子は、どうしたものかとただ途方に暮れました。この噂が由美子の耳に入った時のことを考えると胸が張り裂けそうな思いでした。
(まだ噂でしかない。本当に決まったことかはまだ分からない。)
ふみ子はそう思うことで、少しでも由美子が悲しむ状況から逃げ出そうとしていた。
その日から数日して、由美子が昼の休憩も取らずにミシンを掛けていると、同僚の美代子が近づいて来て言いました。
「由美ちゃん、昼休みくらい休もうよ。話もしたいし。」
「ごめん、ごめん。専務さんから今日中に仕上げて欲しいって言われたから頑張って終わらせようとしていたの。じゃ、少し休憩しようかな。」
由美子の顔は、とても生きいきとして瞳には何の陰りもなく澄んでいました。誰もが自宅に食事に帰っており、休憩室は二人だけでした。
「由美ちゃん、夕べお母ちゃんが言っていた話なんだけど、何でも同級生の総一郎さん、東京の会社を辞めてお婿さんに行くみたいだって。仁賀保にある大きな工場の社長さんの家に婿入りするみたいなの。何でもお父さんが随分お世話になった社長さんから、どうしても一人娘の婿に来てほしいって土下座をされたらしいの。」
由美子は一瞬眩暈を感じながらも、その話を信じることはありませんでした。あの総一郎が自分に何の相談もなく、婿養子に入るなど考えられませんでした。そんな人ではないことを由美子は知っていました。
数か月前の帰省の折の総一郎は、御嶽神社で由美子に確かに言ったのです。
「由美ちゃん、これから由美ちゃんとは隠しごとは一切しないで何でも話し合おうね。僕の両親は由美ちゃんと一緒になることを反対みたいだけど、僕は絶対由美ちゃんと一緒になるからね。だから、何があってもお互いに信じ合おうね!」
あの時、総一郎はまっすぐ由美子の目を見て、そして由美子の両手を強く握って言ったのです。あの時の総一郎は由美子には尊いほどに輝いて見えました。その総一郎が裏切る筈はない。何かの間違いだ。それだけは由美子は確信を持てました。
何とか仕事を時間内に済ませて帰ってきたけれど、夕飯の支度をしながら由美子はこの先どうしたものかと戸惑うのでした。
第4章(1回目) 昭和50年8月
同僚の美代子の話しは確かに衝撃でした。しかし、由美子には総一郎に対する確かな愛がありました。「何があっても信じ合おう」という総一郎への、絶大な信頼がありました。
「総一郎さまへ お元気ですか?お仕事がんばっていらっしゃる様子が浮かびます。私も縫製工場で、専務さんや同僚の美代子さんたちと仲良くしてもらいながら、楽しく毎日を過ごしています。
総一郎さんが何でも話し合おうねと言ってくれ、またお互いに信じ合おうねと言ってくれた時、私はもう数えきれないくらい御嶽神社で泣いたのに、あの時も泣いてしまいました。こんな泣き虫の私をいつも励まし、一緒になろうねとまで言ってくれた総一郎さん。
今の私は、総一郎さんがすべてです。総一郎さんと心が離れたら生きて行けないと思っています。
総一郎さんが何でも話し合おうねと言ってくれたので、勇気を出して話します。
美代子さんが、総一郎さんが仁賀保の大きな会社の社長さんの家に婿養子に入るという噂を聞いたと言うのです。
もちろん私は、そんなことがある筈がないと信じています。誰かの、詰まらない冗談に決まっています。私は、総一郎さんを信じていますので、こんな噂話は平気です。
心配させるようなことを書いてごめんなさい。今度はいつ会えるのか、それだけを楽しみに毎日を生きています。お休みの時、なるべく早く帰ってきてくださいね。
それから最後に、どうかお仕事あまり無理しませんように。総一郎さんの健康のことが一番心配です。食事は、総一郎さんが自炊をされているとのことですが、私も一度くらい、総一郎さんのために料理を作ってあげたくて仕方ありません。将来、一緒になった時のことを考え、お料理の本を買いました。きっと、総一郎さんに喜んでもらえるよう頑張ります。
今度から、お手紙はお友達を介さないで、私あてお送り頂いて大丈夫です。母も、理解してくれておりますので。かしこ 由美子 」
由美子は、以上のような手紙を総一郎に書きました。
投函後数日してからの由美子は、すぐに総一郎から返信の便りが届くことを信じて、仕事を終えると駆けるようにして家路を急ぎ、木製の郵便受けを覗き込む毎日でした。郵便受けに何も入っていないことを知ると、大きなため息をつきながら、仕事が忙しいのだろうと自分を慰める由美子でした。
由美子は、総一郎からの返事がないまま、週に一度は必ず総一郎の健康を気遣う手紙を出し続けるのでした。
第4章(2回目) 昭和49年8月
話しは少し戻ります。総一郎が両親に土下座をしながら、由美子とこの秋に一緒になりたいと懇願しましたが、受け入れては貰えませんでした。
今年の春から東京の芝浦にある北星産業で総一郎は働いています。一流の企業だけあって給料も良くまた福利厚生もしっかりしていました。この会社でなら、由美子と二人で世間並み以上の生活ができるのにと総一郎は思っていますが、あれだけ強い反対をされただけに、焦らずに由美子との愛を育み時間をかけて説得していく以外に方法はないと考えました。
学生の時は夏休みがあり、必ずお盆には帰省しておりましたが、社会人となると自由になる時間は限られて来ました。総一郎の会社での部署は企画部と言うところでしたので各地に出張する機会も多く、また事前に休暇を申請することもなかなか困難でした。
総一郎は、由美子に手紙を出しました。
「拝啓 お元気ですか?僕も元気で仕事に明け暮れています。食事や身の回りのことは、大学の寮での暮らしが長かったので全く平気です。でも、由美ちゃんがいてくれたら、どれほど幸せだろうと時々考えてしまいます。
僕の両親は、由美ちゃんとの結婚に反対ですが、時間をかけて説得していくつもりです。ですので、由美ちゃんは何の心配もいりません。僕に任せて下さい。
お盆には帰るつもりでしたが、入社1年目ですので先輩に遠慮して、今年は帰ることを諦めました。でも、正月には必ず帰りますので、それまで待っていてください。
僕たちには、一緒になるために二人で乗り越えなければならない大きな壁があります。でも、この壁を二人の愛と信頼で乗り越えることが出来た時は、それは2倍にも3倍にも喜びが膨らんで、僕たちは日本一の幸せ者になることが出来ます。
ですので、由美ちゃん!二人で必ず乗り切って、大きな幸せを掴みましょうね!
正月までまだ長いですが、風邪など引かぬよう身体を大切にして下さい。それから、お母さんを大切にして下さい。由美ちゃんには、改めて言うことではありませんが。じゃあ、正月を楽しみに仕事を頑張っていきます。さようなら。」
総一郎は、この手紙を少しでも早く着くようにと、昼休みに郵便局まで行って投函しました。
手紙を受け取った由美子は、総一郎の熱いこころに涙が溢れて止まりませんでした。
第4章(3回目) 昭和50年12月~51年3月
総一郎が仁賀保の大きな会社の社長の家に婿養子に入るという噂を、由美子が聞いたのは8月の頃でした。でも、その3か月前の5月には総一郎と御嶽神社の境内で逢っていたのです。何があっても一緒になろうね、お互い信じ合おうねと手を強く握りながら話した総一郎から、強い男の信念と揺るぎない愛を間違いなく感じた由美子でした。
ですので、その噂を聞いても少しも不安はありませんでした。ただ、総一郎への感謝と健康を気遣う手紙を何度も送りました。しかし、総一郎からの手紙は去年の8月に嬉し涙を流させたあの後は、一度も送られて来ることはなかったのでした。
いつもなら、師走に入ると間もなく、必ず御嶽神社で何日に逢おうねとの連絡が入るはずでした。今日はクリスマスです。鳥海山を一番美しく望めるこの田舎町でも、クリスマスイブにケーキを食べるという習慣はあまり遠くない時期からですが根付いていました。仕事を終えた由美子は予約しておいたお店で小さめのケーキを受け取り、家路を急ぎながらふと思いました。
(総一郎さんと、二人だけのクリスマスイブを迎えられるのは、いつになるのだろう?そんな日が本当に来るのだろうか?)
師走には、総一郎からの連絡は結局ありませんでした。由美子は、とても悲しい元旦を迎えました。総一郎を信じていないのではなく、何か事情があるのだろうとは思いながら、ただ逢えないということが無性に悲しくてならないのでした。
正月もあっという間に過ぎて2月になったある夜、由美子の家に叔母の千代子が自転車でやってきました。
前にもお見合いの話を持ってきた叔母の千代子は、今度もお見合いの話を持って来たのでした。
「由美子、由美子は今年で幾つになるんだ?25にもなるんだろ?女はいつまでも若くはいられない。それに、子供を産むのも、遅くなってからでは体に悪い。そろそろ嫁に行かないか?」
どうやらその見合いの話しというのは、見合いの相手の母親が病気がちで面倒をみていた姉が嫁いでしまい、長男に早く嫁を欲しがっているようでした。ただ家柄は悪くはなく、田畑もこの辺の平均な農家より多くを所有しているとのことでした。
「美代子、お見合いの話しは有り難いが、相手の母親の面倒を見るために由美子を嫁に欲しいと言うんじゃ、由美子が可愛そうだ。それに、由美子は野良仕事なんかしたこともない。千代子、この話はもし由美子が乗り気でも私は反対だ!」
母のふみ子は、由美子の気持ちを代弁してくれました。相手の親の面倒を見るのが嫌とかそういう話ではなく、そもそも由美子には総一郎以外は考えられないことでした。
母のふみ子が叔母の見合い話を断ってくれて、その話は終わりました。しかし、梅の木につぼみが膨らみ始めた頃、今度は伯父が見合いの話を持って来ました。
驚いたことに、母のふみ子は由美子へのその見合い話に大乗り気なのでした。
由美子は、自分の気持ちを分かってくれていると信じていた母のふみ子の豹変ぶりに、ただただ驚きました。
第4章(4回目) 昭和51年3月
由美子は、驚きました。母は、自分の味方だと信じていたからです。惣一郎との恋を認めてくれ、応援してくれているとついさっきまでそう思っていました。それなのに、伯父の秀夫が持ってきた縁談に大乗り気なのです。
伯父の縁談は確かに悪くはありませんでした。相手は町役場に勤めている27歳の青年で、写真を観る限り整った顔立ちはとても優しそうであり、また凛々しさも感じられる感じの良い青年でした。両親は共に学校の先生を職業としているとのことで、嫁を迎えるにあたって一緒に住むのではなく敷地内に息子夫婦のための新居を建てる準備をしているとのことでした。
母がどれだけ気に入ろうとも、由美子には総一郎しか視界にありませんでした。
「伯父さん、私まだお嫁に行く気は全然ないの。心配してくれて、しかもこんないい話を持ってきてくれて、涙が出るほど嬉しい。でも、ごめんなさい。私はまだまだお嫁に行く気がないのに、相手の人に無駄な時間を掛けさせては申し訳ないから、断って欲しいの。本当にごめんなさい。」
由美子は、素直に詫びました。しかし、由美子の話を終えると同時に母のふみ子が少し荒い声で口を挟みました。
「由美子、こんな好い縁談はめったにあるものじゃない。この人はとても良さそうな感じの人だし、まして敷地内に新居を建ててくれると言う話だ。
この私も、お産や何やらの時に、遠慮せずにお前の所に行くことが出来る。私は、この縁談に賛成だ。今、断らないで少し考えてからにしよう。
秀夫兄ちゃん、私が由美子に良く話して聞かせるから、この話進めてくれないか!」
由美子は信じられませんでした。眩暈がするほどの衝撃でした。どうして、どうして、母は私の気持ちを知りすぎているはずなのに!
由美子は表に飛び出し、鳥海山が真正面に見えるいつもの田んぼ道の岩まで走り続けました。岩に腰を降ろしましたが、涙が後から後から絶えることなく溢れてきます。鳥海山は真っ白な雪に覆われ、いつものように勇壮な姿でした。由美子は鳥海山に向い両手を合わせました。
「私は、総一郎さんと一緒になりたい。どうか私の夢が叶いますように!」幼い時から父の姿を知らない由美子にとっては、鳥海山は父親でした。涙が出尽くし、日も落ちて辺りが闇に覆われそうな自分にやっと由美子は家路に向かいました。しかし少し強い風が吹くと倒れてしまいそうな弱々しい姿でした。
由美子が、母に逆らったことは物心ついた時から一度だけでした。総一郎との交際を禁じられた後も、母のふみ子に内緒で総一郎との逢瀬を重ねたとそのときだけでした。母のふみ子は、今回の縁談も良く言い聞かせればきっと由美子は分かってくれるはずだと、そう思っていました。素直で母思いの優しい由美子が、母のためでなく由美子のためを思っての真心を受け入れてくれない筈はない。それを確信していました。
その晩のことです。由美子が母にご飯をよそって渡すと、母のふみ子の顔がいつもの穏やかさがなく、何かを胸の中に押し込んでいるのか、強張った表情に見えました。
「由美子、今日は、どうしたんだ?秀夫兄ちゃんが折角縁談を持ってきてくれたのに、途中で家を飛び出して!こんな良い縁談、滅多にあるもんじゃない。お前の気持ちが分からぬ訳でもないが、おまえを心配してくれる人に背を向けて逃げ出すとは、どういうつもりだ。」
母の言葉からは優しさは感じられず、何が何でも母の考え通りに事を運ぶつもりであるかのような、母の胸の内が感じられました。
由美子が下を向いて黙っていると更にふみ子は続けました。
「由美子、この際はっきり言っておくが、この縁談をこの私は進めるつもりだ。お前が、総一郎さんを好きなのは分かっている。出来ることなら一緒にさせてあげたい。娘の幸せを願わない親はいない。お前は、父親の顔も知らずに育ったけれど、素直な良い娘に育った。お前には、幸せになってもらいたいが、総一郎さんとの結婚は諦めろ。総一郎さんの親が絶対許してはくれない。
総一郎さんはお前と一緒になるためなら、きっと佐々木家を飛び出すだろう。お前も総一郎さんも、それが一番幸せの道だと思うに違いない。
そうなると総一郎さんは東京の会社を辞められない。当然お前も東京に行くことになる。私は我慢するとしても、総一郎さんは一生佐々木家の敷居をまたぐことが出来ない。孫が出来ても親に見せることも出来ない。孫の顔を親に見せられない息子ほど、親不孝な子供はいない。お前も、年を取ってその時になれば分かる。
それに総一郎さんの父親は、恩義ある人の土下座までも拒んだ酷い人と噂が立ち、これからの世間の見方も変わって生きづらくなるに違いない。
二人が幸せなら親がどうなっても構わないという生き方が、本当の幸せと言えるのだろうか?二人の我が儘なだけじゃないのか?
そう言えば、お前は総一郎さんとはしばらく会っていないようだが、何かあったのか?総一郎さんも親に反対されて、泣く泣く由美子と別れようとしているのではないのか?」
由美子は涸れたはずの大きな涙をまた流し始めました。
(そんなことはない!総一郎さんに限ってそんなことはあり得ない!)
由美子は心の中で叫んでいました。
第4章(5回目) 昭和51年4月末
そろそろ桜の花の蕾みも膨らみ始め、もう直ぐ春本番が訪れようとしています。
伯父の縁談の話しが来てから、由美子と母ふみ子との会話が少なくなってきました。母は夕食のとき、いつも繰り返し同じ話をします。
「由美子、お見合いの件だけれど、人には相性というものがある。いくら周りが良いと思っても、当人同士の気持ちが合わなければ、どんなに条件が良くても幸せにはなれない。それは、私が今まで多くの人を見て来て感じたことだけれど、お前がお見合いをしてどうしても嫌なら断っても構わないから、一度だけ会ってみないか?」
由美子は返事をすることもなく、一筋の涙を流しながら俯くばかりでした。
由美子は、伯父が見合いの話を持ってきた翌日から、総一郎宛ての手紙を何度も出しましたが、返事は返って来ませんでした。しかし、由美子の総一郎への信頼は揺るぐことはありませんでした。
「総一郎さん、お元気ですか?私も元気に頑張っています。
何度もお手紙を差し上げたのですが、総一郎さんからのご返事がありませんので、私はとても心配しています。
私は、今本当に困っています。伯父からのお見合いの話しに母が乗り気なのです。
『総一郎さんのことを好いているのは知っているし、出来ることなら一緒にさせてあげたいが、所詮お前が佐々木家に嫁として入ることは、相手の両親も世間も決して許してはくれない。駆け落ちでもしたなら、尚更親不孝になる。どうか総一郎さんのことは諦めて、今度の見合いを受けてくれ!』
毎晩、こうして私にお見合いをするように話すのです。私は、母から受けた恩義には必ず報いるつもりではいますが、それとこれとは別な話です。私が一生を共にしたい方は、この世界の中で総一郎さんただ一人です。どうか、ご返事をください。大丈夫だ!もう少し待ってくれ!必ず迎えに行くと言ってください。その一言を聞けば、どんな辛いことも耐えられます。母の言葉に涙を流さずに、耐えることが出来ます。どうかお願いします。かしこ 由美子より」
殆ど同じ内容の手紙ですが、昼休みに郵便局まで自転車で行き、2日に1通の割で投函しています。そして、仕事が終わり家に帰ると真っ先に郵便受けに走ります。ですが、いつも空のままで由美子は落胆してしまいます。もう手紙の数は、20通を超えましたが返事は1通もありませんでした。
ある晩のことです。母が、初めて見る形相をし、由美子に声を張り上げました。
「由美子、私はお前のためを思って、見合いの話を毎晩しているけれど、お前は聞く耳を持たない。私にとってお前は自慢の娘だけれど、でももう待てない。どうしても見合いが嫌ならこの家から出て行け!総一郎さんの所でも、どこでも構わないから、見合いが嫌なら明日にも出て行け!」
母は、鬼のような形相でした。由美子は、あまりの母の姿に驚愕しました。出て行けと言われても、由美子には行くところがありません。総一郎からの返事もなく、東京へ逃げる訳にもいかないのです。
次の日の朝、由美子は母に観念したように言いました。
「私、お見合します。」
たったそれだけを言いました。その言葉に母は、静かに言いました。
「由美子、じゃあ秀夫伯父さんに頼んで、良い日を選んで先方と進めて貰うから。」
母の顔は、安堵したという表情でもなく、これで良かった、これが由美子のためなのだと、そう自分に言い聞かせているかのようでした。
お見合いの日は、5月半ばの大安の日に決まりました。由美子は、総一郎からの返事がないまま、更に手紙を出し続けました。
「総一郎さん、お元気ですか?私は、総一郎さんを疑ったことは一度もありませんが、私はついにお見合いをしなければならない状況になってしまいました。お見合いが嫌なら、家を出て行けと母は言うのです。私には行くところがありません。総一郎さんが、東京に出て来いと言うなら、私は喜んで今すぐ家を出るでしょう。でも何度お手紙を出しても返事を頂けないのですから、東京へ押しかける訳にもいきません。
総一郎さん、私はどうすれば良いのでしょう?もちろんお見合いをしてもお断りをするつもりです。母も、相性が一番だから、もし合わない人だと思うなら断っても構わないと言ってくれています。それでも、不安なのです。私は弱い女です。母を、伯父を捨ててまで、断れないかも知れないと不安なのです。
お願いです。総一郎さん、ご返事をください。私は仕事が終えて家に帰ると、毎日郵便受けに走ります。そしてため息をつきます。総一郎さん、どうか私を助けて下さい。私の人生には、総一郎さんしかいないのです。助けて下さい。お願いします。かしこ 由美子」
由美子が待ち望んだ手紙は、1週間が過ぎても、そして2週間も過ぎても届くことはありませんでした。
第5章(1回目) 昭和51年5月半ば
総一郎に出した手紙の数は20通を超えていますが、総一郎からは何の連絡もありません。
もう5月の半ば、明日は伯父の持ってきたお見合いの日です。由美子は、母が見合いをしないのなら出て行けとの言葉に泣く泣く承諾したお見合いですから、最初から丁寧に断るつもりでした。
お見合いは、隣町にある少し洒落たレストランで行われました。由美子は、母がいつの間にか用意した着物を着て行きました。伯父に連れられて行くと、見合いの相手と親戚だという年配の男の人が二人先に来ていました。
由美子の伯父は、「お日柄もよく、今日はおめでとうございます。」などと、よく意味の分からない挨拶をし、とにかく4人は席に着きました。
由美子は相手の男の人の顔を見ることはありませんでした。伏し目がちに、ずっと握りしめたハンカチを見つめていました。
親戚の叔父と言う人が見合いの相手の紹介を始めました。見合いの相手は、信彦と言い、役場に勤めてもう直ぐ10年になるとのこと、また仕事も出来て職場では将来を見込まれているなどと話しました。また、人柄は穏やかで、とても皆に好感を持たれていること等も付け加えました。
由美子の伯父は、由美子が幼い時に父親が亡くなり随分苦労したが、性格は素直で、また父譲りの整った顔が自慢だなどと由美子を褒めました。
少しして、食事が運ばれてきました。お酒も運ばれてきましたが、信彦はお酒が飲めないとのことで、付添いの二人だけが徳利を互いに交わして、盛んに二人を「似合いの夫婦だ。」とまるで婚約が成立したような言い方をしました。
由美子が不意に顔を上げた時、信彦の目と合いました。お互い、ほんの僅かな時間でしたが、視線を外すことなく見つめ合いました。確かに、信彦と言う青年は優しく、また生き方に信念を持っているという風な凛々しさも感じられました。しかし、それ以上の興味は持てませんでした。
由美子は、このお見合いの席にいることを恥じていました。心から愛する人がいるにも拘わらずお見合いをすることは、どんな事情があるにせよ、裏切り行為と思われても仕方がないと、総一郎への詫びる気持ちで一杯でした。
その日は食事をした後、徳利を交わして盛り上がっている二人の勧めで、近くの稲荷神社に二人は行きました。しかし、由美子も信彦もお互い積極的に話しかけることはありませんでした。
お見合いが済んだ数日後、由美子とふみ子が夕食を済ませ寛いでいる所に、伯父の秀夫がやって来ました。
「由美子、見合いの話しだけど、先方はお前が良ければ、ぜひ嫁に欲しいそうだ。信彦さんは、お前が優しそうな、そして口数が少ないが頭の良さそうな人に見えたと言っていたぞ。」
伯父の秀夫は、嬉しそうに一気にしゃべりました。それを聞くと、母のふみ子も興奮しながら言いました。
「それは良かった。こんな好い縁談、滅多にあるもんじゃない。相手に気に入られて、何よりだ。良かった。これで、私もやっとひと安心だ。」
伯父の秀夫は、自分の手柄とでもいうように言いました。
「信彦さんの両親は、お互いに良ければ秋の収穫が済んだあと、少しでも早く祝言を挙げたいそうだ。」
由美子は、じっとして何も話しませんでした。ただ、二人の喜びようを見ていると、この場は断われる雰囲気ではないと諦めたのです。
由美子は総一郎からの連絡を待ちましたが、一向に返事がありません。こうしている間に、縁談の話しは由美子を超えたところで着実に進んでいるのです。
由美子は焦り、総一郎への手紙をただ書き続けるだけでした。
第5章(2回目) 昭和51年6月初め
見合いに同席した信彦の叔父という人が正装をしてやって来ました。信彦側の今後の進め方の希望を伝えるためでした
「由美子さん、相手の両親は信彦を信頼していて、信彦が気に入ったのなら間違いはないとよろこんでいるよ。来月にも結納をして田んぼが一段落した10月に式を挙げたいとのことだ。ふみ子さん、どうだろう?」
「そりゃ、こういう事は先延ばしせず一気に進めた方が、私も早く肩の荷が降ろせると言うものですよ!」
母のふみ子は少し上気した顔で言いました
由美子は黙って聞いていましたが、覚悟を決めたように信彦の叔父に向かって言いました。
「私からお願いなんですが、高橋さんと一度二人だけで会わせて貰えませんか?」
この言葉に母も親戚の叔父という人も一瞬顔を紅潮させました。
「うんうん、それが良い。一度会っただけでは何も分からないだろうし。うん、それが好い!段取りは由美子さんの都合に合わせるから大丈夫!」
信彦の叔父と言う男は、この縁談もこれで上手くいくだろうと満面の笑みを湛えて言いました。
由美子は惣一郎を信じていました。何か訳があって手紙の返事をくれないのだろうと考えていました。
信彦の叔父から来週の日曜日に、やはりこの前見合いをしたレストランを指定してきました。ただ、今回は由美子の希望で食事ではなく、お茶を飲みながらの団欒という設定となりました。
その日曜日が来ました。午後2時の約束です。今度は着物ではなく由美子はブラウスにカーディガンというラフな格好で出かけました。一階の入り口から良く見えるテーブルに信彦はきちんとした身なりで座っていましたが、由美子を見つけると慌てて席を立ち、反対側の椅子を引き由美子に腰を降ろさせました。こんなところからも、信彦の優しさが感じられ、総一郎の存在がなければ由美子も好意を持ってしまうかも知れないと、一瞬思いました
信彦はまた会う機会を作ってくれた由美子にお礼を言い、両親にいかに由美子が素晴らしい人かを一生懸命に話した様子などを聞かせました。
由美子は、僅かに微笑みながらも自分の本当の気持ちを話すタイミングを図っていました。
信彦が新居の間取りの話しに入ろうとした時、由美子は口を開きました
「今回頂いたご縁は、私にはもったいない程の話しで、母も大変喜んでいます。
ですが、あのぅ・・大変申し訳ないのですが、私には将来を誓い合った人がいるのです!ですので、そのお詫びを申し上げたくて、今日お時間を頂きました。誠に申し訳ありません。」
それだけを、やっとの思いで由美子は信彦に告げました。
第5章(3回目」 昭和51年6月初め
由美子の話を聞いた信彦は、気落ちしたようなちょっと引きつったような顔を一瞬しました。しかし、信彦は何としてもこのまま終わりたくないとの強い思いから、少しでも可能性を探り出そうと必死で数分の間、目をつぶりながら考え、あるアイデアに辿り着いたようでした。
「由美子さん、由美子さんのこころは良く分かりました。でも、それならどうして僕とお見合いをしたのですか?何か事情があったのでしょう?」
信彦の言葉は、由美子を責めているというよりも、由美子のために力になりたいという善意の想いが感じられる言いかたでした。由美子は、たった2度目の信彦との出会いでしたが、暖かい人情味と誠実な人柄を信じ、これまでの総一郎とのことや母とのいきさつのことなどを正直に話しました。
じっと静かに由美子の話を聞いていた信彦の目頭には光るものがありました。
「由美子さん、良く分かりました。総一郎さんと一緒になれるよう、僕にできることがあったら言ってください。それが由美子さんのためになるなら、悔しいけれど、お役に立ちたいと思います。
でも正直、僕も由美子さんとのこの縁を終わりにしたくはないと思っています。私の人生を二人三脚で生きて行ってほしい人は、由美子さんしかいないと思っているのです。今日で2度しかお会いしていませんが、僕には由美子さんのすべてが見えるような気がしております。神様が、僕に与えてくれた大切な縁だと思っているくらいです。
ひとつ提案があります。今日から3ヶ月の間に、由美子さんは総一郎さんと共に、由美子さんのお母さんや、総一郎さんのご両親の前で二人の決意を表明して下さい。お二人の決意が示され、皆様に認めて頂いたのなら、僕は由美子さんを潔く諦めます。この縁も、単なる神様のいたずらと諦めます。
ですが万が一、総一郎さんのこころに変化があって、お二人にその誓いが守れなくたった時、その時は由美子さん、僕との結婚を前提にお付き合いをして下さい。
これからの3ヶ月の間のことは、由美子さんのお母さんや僕の両親と叔父に上手く話して時間を稼ぎます。また、総一郎さんと一緒になれることを前提に、その辺のところも後から問題にならないように立ち回りますから、心配しないで総一郎さんと1日も早く逢って、この状況を話してください。」
何と信彦は、総一郎との結婚を応援するというのです。でも、総一郎との縁が切れた場合は、信彦を生涯の伴侶として考えて欲しいというのでした。
第5章(第4回目) 昭和51年6月半ば
何と賢明で、そして思いやりにあふれた人だと由美子の目頭も熱くなり、信彦の顔がぼやけて見えました。
信彦に感謝しながらも、由美子は考えていました。3ヶ月の時があれば、総一郎と会い二人の誓いを大人たちに宣言することは、十分可能だと。
由美子は充分な自信と総一郎への厚い信頼を胸に、信彦の提案を了承しました。
それから数日後の夜、信彦が叔父と一緒に由美子の家にやって来ました。信彦は家には上がらずに、由美子の母にこう話しました。
「二人で相談したのですが、今後3ヶ月間、由美子さんとお付き合いをさせて頂いて、本当に二人とも幸せになれるかを考えたいと思っています。なので、結納とか挙式のことは、3ヶ月が過ぎてから、本当に二人が結婚したいと思った時から準備したいと思っています。もし、二人が一緒になってもお互いのためにならないと判断した時は、白紙に戻したいと考えています。これは二人で決めたことですので、よろしくお願いします。」
それだけを言うと、信彦と叔父は帰って行きました。母も、結婚してから相性が悪く由美子が不幸になるより、確かにその通りだと感服した様子でした。
由美子の母に述べた言葉を今度は、信彦は自分の両親にも告げましたが、同じように賛成こそすれ、反対はありませんでした。
由美子は決心しました。数え切れないほどの手紙を送ったにも関わらず、総一郎からは梨の礫です。3ヶ月という期限は決して長くはなく、由美子も本腰を入れなければと自分に言い聞かせました。
由美子は普段可愛がってもらっている専務さんに休暇を2日貰い、日曜日から火曜日までの3連休を作り、東京の総一郎のアパートを訪ねることにしました。母には、山形にいる中学の時の友達の家に遊びに行くと嘘をつきました。悲しい嘘ですが、今は何より総一郎の心を確認することが、二人の人生に幸福をもたらすのであり、小さなことに拘っている状況ではないと由美子は強い気持ちで東京に向いました。
初めての東京です。前もって買っておいた東京までの電車の路線を調べるための小冊子と、また都内の地図を麻のバックに詰め込みました。また、総一郎からの手紙は、大切に胸のポケットにしまいました。この手紙の裏に書いてある住所こそ、総一郎に会えるための唯一の手掛かりです。
郵便局から十分と思われうる金額を引き出し、手さげバックに入れました。
東京には明日の午後2時頃の到着を考え、羽後岩谷駅を午後1時過ぎの電車に飛び乗りました。
路線図と時刻表を眺めながら、何度も電車を乗り継ぐたびにこれで良いのかと不安でしたが、少しずつ総一郎に近づいているという思いが、不安を忘れさせました。
東京の大森駅に着いたのは午後の3時を回っていましたが、さっそく大田区の地図を広げ、中央3丁目を探しました。バスもありましたが、地図では20分も歩けばつく筈でした。
バス通りから、少し裏通りに入ると、狭い路地にくっつくように家が、そしてアパートが密集しています。総一郎のアパートの近くまで来ると、もう夕方になっていました。初めての都会での心細さで、由美子は藁にもすがる思いで、出会う人に誰彼かまわず声を掛け、アパート名を訪ね歩きました。
もう既に10人目位かと思うころ、高齢の女性に声を掛けると丁寧にもアパートまで案内してくれました。アパートは、木造モルタル作りの小さなアパートでした。
玄関に入ると、住人用の郵便受けがあり、「佐々木総一郎」の名前は確かにありました。思わず安堵のため息をし、総一郎の部屋を探しました。1階にはなく、2階に上がってみると総一郎の名札が掛かった部屋が確かにありました。ノックをしても留守の様でした。生憎日曜日のため、住人は誰一人いないようでした。由美子は、ますます心細くなりましたが、暫く待つことにしました。
どのくらい時間が経ったのか、総一郎の部屋の前でついウトウトしてしまった由美子でした。ふと人の気配で目が覚めました。すぐそこに中年の女性が立っていました。
「すみません。この部屋の佐々木さんをご存知でしょうか?」
由美子の問いかけに、怪訝そうな顔つきで、「佐々木さんは去年の夏ごろから、姿が見えないよ。どうしたのかね?」とそっけなく答え、隣の自室に入ってしましました。
すっかり途方に暮れた由美子は、仕方なくまた大森駅の方に引き返し、一晩泊めてもらうための宿を探すことにしましたが、宿の探し方も分かりません。由美子は、交番に入り警察官に事情を話し泊まるところを探してもらいました。まだ若く優しい警察官は、女性の一人客ということも付け加えてくれたので、由美子は安心して地図を書いても貰った宿に着くことが出来ました。
宿の女将が運んできたお茶を啜りながら、どうしたら良いものか悲観に暮れる由美子でした。
終 章(1回目) 昭和51年6月半ば~7月初め
由美子はすっかり混乱してしまいました。総一郎に会いたくて、はるばる訪ねて来たことに後悔はありませんが、総一郎は去年の夏頃から姿が見えないというのです。
でも、不思議としか言いようがないのです。御嶽神社で会い「お互いに信じ合い、何でも話し合おう」と総一郎と約束したのは、昨年の5月でした。そして、総一郎のお見合いの話を聞いたのは8月のころ。そして、由美子が手紙を送り始めたのもその頃で、既に数十枚の手紙を送っているのです。昨年の夏に、仮に総一郎がどこかに行ったとしても、郵便受けには由美子の手紙が入っていなければならない筈です。
また由美子は、頭を抱えてしまいました。眠れぬままに一夜を過ごし、宿の朝食に殆ど手を付けることなく、また総一郎のアパートに向いました。昨日と同じアパートは静かで誰もいないようでした。
由美子は為す術もなく、すれ違う人と何度もぶつかりそうになりながら、大森駅に向かい、後ろ髪を引かれる思いで京浜東北線に乗り込みました。
母は何も聞きませんでしたが、次の日に信彦から電話が入りました。会社が昼休みのため、受話器の傍には同僚の美代子がいるだけでした。
「由美子さん、総一郎さんとお逢いになりましたか?二人で、お互いの親の前で、結婚の宣言をするということになりましたか?」
由美子は信彦には、正直に話をしました。信彦の話し方は好奇心でもなく、また二人の交際が壊れれば良いというような思いではなく、真から心配している様子が伺えました。由美子の頬から涙が溢れました。
「手紙が届いていないのだけはおかしいな。でも、きっと何かの事情がある筈だ。あまり心配しなくても大丈夫だよ。また、電話掛けさせて貰うから。出来ることがあったら言ってね。」
信彦は由美子の涙に辛い気持ちになって、早々と電話を切りました。でも由美子には、信彦の気持ちは有り難かったのでした。誰にも相談できず、総一郎の身を案じ堂々巡りだけの由美子だったからです。
鳥海山を囲む山並みが緑一色になり、蝉の声がせわしい夏がまたやって来ました。総一郎のアパートの住人の話しからすると、総一郎がアパートを出てからもう1年になる筈です。由美子は、総一郎の実家に足を運ぶ勇気は持ち合わせてはおりませんでした。行けば何かしらの情報が掴めるはずだとは思いながら、結婚を強く反対されている自分の姿を総一郎の両親に見せることは、総一郎のために、また自分のためにもならないと諦めているのでした。
東京のアパートに行っても姿が見えない、また数十通の手紙を出しても返事が来ない!それなのに、総一郎からは何の音沙汰もない。ここ10日間眠れない夜を過ごし、すっかりやつれてしまいました。思考力も鈍くなり、総一郎とのあの御嶽神社の逢瀬も、夢の出来事であったかのような錯覚に陥っている由美子でありました。
母のふみ子は、由美子の気持ちに気付いていました。総一郎と由美子の間の縁はもはや断ち切れたのだと不憫に思い、信彦との婚礼を早めることが由美子にとって一番幸せな方法だと信じて疑いませんでした。
ふみ子は見合いを持ってきた兄の秀夫に事情を話し、婚礼を急ぐ算段を相談しました。二人は、信彦の両親に何とか早めに祝言を挙げたい旨を、やはり見合いに立ち会った信彦の叔父に伝えました。その話を聞いた信彦の両親は、もろ手を挙げて喜びました。かつて信彦には交際していた女性の気配もなく、このまま三十路へと進む息子を黙って見ていることは、親としても辛いことでした。
母のふみ子と伯父の秀夫、それに信彦の両親と叔父は、ある日隣町の料理屋に集まり、今後の相談をすることにしました。由美子と信彦には話しをせずに、決めてしまうつもりでした。そのことには誰一人として、反対する者はいませんでした。
終 章(2回目) 昭和51年7月初め
料理屋に揃った5人は皆、由美子と信彦の婚礼に積極的でした。
先ず信彦の叔父がふみ子に向って言葉を発しました。
「信彦は、由美子さんを見合いの席で、いっぺんに好きになってしまったらしい。見合いの日、由美子さんたちと別れてから、あんな人が自分の嫁になってくれたら、こんな幸せなことはないと、何度も言っていましたよ!」
ふみ子はとても嬉しそうな表情をして聞いていましたが、今度は信彦の両親にしみじみ話しかけました。
「由美子は、幼い時に父親に死なれ、とても貧しい生活をして来ました。中学3年の時、由美子の担任の先生が由美子は成績が良いからどうしても高校に行かせてやって欲しいと家を訪れ、何度も頭を下げてくれました。でも結局、由美子には可哀そうな想いをさせてしまいました。親として不憫でしたが、今回信彦さんのような方と祝言を挙げさせて頂けましたら、亡くなった主人にも胸を張って報告できます。どうか、この縁談がまとまります様、どうかどうかよろしくお願いいたしますう。」
ふみ子は途中から感極まったという表情で、涙と鼻水で顔をくしゃくしゃにさせ、手さげカバンの中から急いでハンカチを出して拭いました。
信彦の父親の喜一が、穏やかな笑みを浮かべてふみ子に話しかけました。
「由美子さんのお母さん、由美子さんをここまで育てるために、大変なご苦労をされたことと思います。その由美子さんを信彦のお嫁さんとして頂けることは、とても有難くどんなに感謝しても足りません。私も、妻の智恵子も由美子さんを自分の娘と思って大切にさせて頂きます。こちらこそ何卒よろしくお願いいたします。」
今度は総一郎の叔父が顔を紅潮させて、少し大きな声で話しました。
「由美子さんと信彦の縁談に両家が喜んでいるのだから、こういうお目出度い話しは急いだ方がいいと思う。どうでしょう?結納は、来月8月10日大安の日ということで。そして祝言は、親戚の者たちの都合もありますので、稲刈りなどの農繁期に入る前の9月の半ばということで如何でしょう?」
この信彦の叔父の提案に一同意義を唱える者はなく、一様に頷きました。今度は信彦の母の智恵子が口を開きました。
「信彦の新居の完成も、急げば今年中に何とかなるでしょう。その間は役所の近くにあるアパートを借りてもいいし、今の家の部屋も余っているから一緒に住んでも構わない。まあ、それは当人同士に決めて貰えば良い話ですが。あっ、そうだ!そういえば、信彦の誕生日は9月の15日ですから、婚礼も同じ日にしたら当人も喜ぶと思いますが、いかがでしょう?」
こうして由美子と信彦の婚礼は、二人が不在のまま着実に進んでいくのでした。
終 章(3回目) 昭和51年7月初め
表情から笑顔が消えて、塞ぎ込むことが多くなって来た最近の由美子に、ふみ子はとても心を痛めていました。先日の料理屋の相談の結果を何とか上手に話さなければと、ふみ子は二日悩みましたが、結局ありのままを話す以外に考えが浮かびませんでした。
夕飯を終えた由美子が、ただ眼だけを雑誌に向けていましたが、心は宙を彷徨っているかのようでした。ふみ子は決心して由美子に声を掛けました。
「由美子、お前最近疲れているようだけど、大丈夫か?話があるんだけどな、お見合いの相手の信彦さんの両親から、秋には婚礼を挙げたいと言ってきたんだけど、私もそうしたいと思って、ぜひよろしくお願いしますと言ってしまったんだが、由美子もそれでいいな!」
由美子は、母は自分とは違う別な誰かに向って言っているようなそんな気がしました。母は、由美子の同意を求めているようでしたが、由美子は発する言葉を探すことさえも億劫でした。黙って、雑誌に目を向けたままでした。
「なあ、由美子。お前が総一郎さんと一緒になりたいと思っているのは、この母には分かる。私も出来ることなら、それが一番だと思っている。でも、総一郎さんは、仁賀保の大きな会社の社長さんの婿養子に入るという話だし、お前もいつまでも若くはいられない。今回お見合いをした信彦さんは、お前に贅沢をさせてはくれないかも知れないが、お前に辛い想いをさせることはないと思う。それに、信彦さんのご両親も、お前を実の娘だと思って可愛がってくれるそうだ。その上、今年中に新居も建ててくれるそうだ。こんな有難い話は、長い人生の中でも何度もあることじゃない。由美子、私からもお前に頭を下げて頼む。どうか、この母を安心させると思って、信彦さんと夫婦になってくれないか!」
ふいに由美子は目頭が熱くなり、涙が溢れてきました。しかしこの涙がなぜ流れるのか、その理由は由美子にも分かりませんでした。
去年の8月に総一郎の婿養子の噂を聞き、真意を確かめるという意味ではないにしろ数十通送った手紙には返事がなく、遥か遠い東京のアパートに出向いても姿の見えない総一郎。由美子は胸が裂けるような想いに打ちひしがれた、この弱い女の心を支えてくれる誰かの力を求めている自分に気付いていませんでした。
その晩は、ふみ子もそれ以上由美子に迫ることを控えました。
次の日の昼時、信彦からまた電話が入りました。同僚の美代子は気を利かせて、鼻歌を歌いながら部屋から出て行きました。
「由美子さん、お母さんから話を聞きましたか?昨夜、両親から聞いたのですけど、結納の日も婚礼の日ももう決めてしまったそうです。僕は、由美子さんから、はっきりした返事を貰っていないのに、何で勝手に決めたんだと腹を立てて、食って掛かりましたが、由美子さんのお母さんも了承していることだからと言われ、それ以上何も言えなくなりました。もちろん、僕には嬉しいことですが、由美子さんが心底納得して、僕のお嫁さんになってくれるまで僕は待つつもりです。その後、総一郎さんとは、連絡は取れませんか?」
お互いの両親が、結婚する当人たちの承諾も得ずに、結納から婚礼の日までも決めてしまったという事実に、由美子は確かに衝撃を受けましたが、心の隅で『これで良かったのかも知れない。』と安堵のような想いが一瞬芽生えていました。
終 章(4回目) 昭和51年7月半ば
次の日曜日の午後2時過ぎに、お見合いをそして2度目にも会ったレストランに由美子と信彦の二人の姿がありました。
逢瀬という言葉にはまだ早すぎる二人の姿は、由美子からの申し出を信彦が快諾したことに始まります。
由美子は、素直に胸の内を語りました。
「信彦さんに聞いて頂きたいのですが、耳障りなこともお話しするかと思いますが、どうか私の話を聞いて欲しいのです。
母が言うのには、私には幸せになって欲しいけれど、総一郎さんとの結婚は諦めろと言うのです。それは、総一郎さんの親が反対していますから、どうしても無理だというのです。二人が駆け落ちしても、育てて貰った恩を裏切り、親を苦しめる最も大きな親不孝だと言うのです。親に、孫の顔を見せられないような結婚が果たして幸せと言えるのかというのです。総一郎さんのお父さんは、義理ある人から、婿養子に欲しいと土下座までされたと聞いています。総一郎さんのお父さんにも、大きな犠牲を強いることになってしまうというのです。親を苦しめてまで添い遂げても、それが本当の幸せか良く考えろと言われました。
私は、何が何だか分からなくなりました。総一郎さんには、もう二十通以上の手紙を送っていますが、返事がありません。総一郎さんと最後に逢ったのは、去年の五月です。『お互いに信じ合おう』と言ってくれましたが、どうして返事をくれないのでしょう。先月の半ばに、東京まで行きました。総一郎さんのアパートを訪ねるためです。
初めての東京は迷うばかりで、総一郎さんのアパートに着いたのは夕方近くになってしまいました。総一郎さんの姿はありませんでした。次の日に、もう一度訪ねてみましたが、住人の方の話しだと去年の夏ごろから姿が見えなくなったと聞きました。不思議なことに、郵便受けに、私の手紙は入っていませんでした。
私はすっかり疲れて帰りました。その後は、総一郎さんとのことは夢の出来事なのか本当のことだったのか、私には分からなくなりました。
総一郎さんが、少しでも私に愛情をお持ちになっているとしたら、こういうことはあり得ないと思えるし、いや何か事情があるのかも知れないと、私の頭の中はすっかり混乱して、ふらふらと日中でも夢を見ているような気分です。
今日、信彦さんにこうしてお聞きになりたくないようなお話をさせて頂くのは、私はこれ以上、母を苦しめたくないからです。
親兄弟や親せきの人に祝福されない結婚は、やはり本当の幸せとは言えないと、母の言う通りだと思えるようになったのです。総一郎さんも、私と一緒になって親兄弟と絶縁し、由緒ある実家の敷居をまたげないようでは、私が総一郎さんを苦しめていることになります。総一郎さんを苦しめる結婚なら、私は身を引こうと思うのです。
信彦さん、どうかもう少し我慢して聞いて下さい。私が、信彦さんと結婚するとしたら、誰をも苦しめないどころか、私の母や信彦さんのご両親、またお互いの親戚の方に喜んでいただけます。このことは結婚する二人にとっても、とても大切なことだと思います。
こういう言い方は、信彦さんに大変失礼なことは重々分かっております。信彦さんの気持ちを無視した、ただ身近な人たちへ迎合した、結婚の本質を忘れた愚かな女だと思われるでしょう。
この数か月、食事も喉を通らない毎日でした。夜は、しょっちゅう目が覚めて、明け方まで眠れない毎日でした。
私の父親は私が幼い頃亡くなって、物心がついた時から、私は辛い時にはいつも鳥海山に話しかけて来ました。そうすると、いつも心が安らぐのです。鳥海山は、私の父親だと今でも思っています。
でも、今回は誰かに助けて欲しいと思いました。私も、やっぱり女です。この苦しさから、誰かに救って欲しいと思いました。
怒らないで聞いて下さい。信彦さんと会ったお見合いの日に、とても信彦さんは人としても素晴らしい方だと思いました。でも、その時はそれだけでした。お電話をいただき、総一郎さんと将来の約束をしているからと、お断りをさせて頂いた時に、応援して下さるとまで言ってくれました。とても、有難いお言葉でした。総一郎さんという存在がなかったら私は喜んで承諾させて頂いたと思います。
今の私は、信彦さんに相応しい結婚相手とは言えない状態です。お時間を頂いて、信彦さんの愛を素直に受け入れられるようになるまで待っていただけたらというのが、今日お会いして頂いた理由です。勝手な事ばかり申し上げました。」
そう言って、由美子は信彦に深々と頭を下げました。
しばらく二人に沈黙の時が流れ、やっと信彦が穏やかな笑みを浮かべて、由美子に語りかけました。
「由美子さん、どうもありがとう。何一つ隠さず、心の内を打ち明けてくれて、僕はとても感動しています。僕は、益々由美子さんが好きになりました。
僕の考えを、お話しします。由美子さんが、総一郎さんのことを忘れられないのは、当たり前のことです。忘れられるまでには、お付き合いした倍の時間が掛かるそうです。ですからそのことは、僕は何とも思っていません。でも、不思議ですね。総一郎さんは、いったいどうしたのでしょう?このままでは、由美子さんも身動きが取れないとは思いますが、どうでしょう?親が決めた通りに、結納そして婚礼と予定通りに進めませんか?
僕に、由美子さんの辛さを救ってあげる自信はありませんが、精一杯努力します。
結婚しても、由美子さんが、総一郎さんを忘れ、僕を生涯の伴侶と認めて貰えるその日まで、寝室は別にしましょう。そして、その日まで夫婦の契りは待つことにします。いつまででも、僕は待ちます。由美子さんの真実の愛が得られるその日まで。」
由美子はハンカチで顔を抑え、周りに聞こえぬように嗚咽していました。
終 章(5回目) 昭和51年8月~9月15日
由美子と信彦と互いの親、そして仲人となった由美子の紡績工場の専務さんという僅かな人たちでの結納も無事済んで、あっという間に祝言の日が訪れました。
今回は多くの招待者の祝福を受けて、隣町のそれ程大きくないホテルで由美子と信彦の結婚式は執り行われました。式の途中、由美子は何度も涙を流しましたが、周りの者たちは皆嬉し涙と疑いませんでした。
「きれいな花嫁さんだね!」
あちこちから感嘆の声が上がりました。この日、親戚の者から借りた着物を着た母のふみ子は、それらの声を聞くたびに満面の笑みを浮かべていました。
花婿の信彦も緊張の中にも喜びを抑えられず、友人たちの祝福の声に涙ぐむシーンも見られました。
三々九度の杯の時の由美子は、杯を持つ手が震え、注がれた杯に口を付けることを一瞬躊躇しました。それに気付いた信彦の哀願するかのような目配せに、意を決してやっとその儀式を終えることが出来たのでした。
式場が酒盛りで賑やかさも頂点に達したころ、由美子は仲人の専務さんご夫婦と三人、待たせておいたタクシーに乗り、御嶽神社に向いました。
このことは、予め信彦にもお互いの両親にも許可を得てありました。それは、結納の儀式が済んで、一同が寛いだその時に、由美子は「お願いがあります!」と全員の前で頭を下げたのです。
「お願いがあります。結婚式の日に、私はどうしても御嶽神社にお参りをしたいのです。私には、御嶽神社には幼い頃からの思い出があります。御嶽神社を詣でることは最後かもしれないので、結婚式の日に最後の挨拶をしたいのです。」
この由美子の願いに異を唱える者は誰一人いず、却って仲人の専務は「最近の若い人が町の神社仏閣にお参りするなどという姿を見たことがない。いや、若い由美子さんが、これほど信心深いとは素晴らしいことだ。」と褒め称えました。その時、信彦の母智恵子が、「それなら宴たけなわの頃、タクシーを用意させて頂きますから、専務さんご夫婦と一緒にどうかしら?三十分もあれば行って来られるでしょう。」と提案し、みな頷いた。
御嶽神社に着いた由美子は、タクシーから降りると専務の奥さんに手を取られ境内に入りました。先ず水舎(みずや)で手を洗い、拝殿の前に立ちました。
由美子は軽くお辞儀をし、懐に用意してあった和紙で包んだお賽銭を置き、鈴を鳴らしました。神社の柏手は二礼二拍手一礼と決まっています。由美子は、最後の一礼の時に、心の中で念じました。
「総一郎さん、私は信彦さんに嫁ぎます。これが、これが二人にとっての最良の道だと信じています。許しは乞いません。総一郎さん、幸せになってください!」
式場に戻ってみると、宴はたけなわで、由美子が席を外したことさえ気付かぬほどでした。
こうして、鳥海山が良く見えるある町の片すみに、一組の夫婦が誕生したのでした。
終 章(6回目) 昭和51年9月下旬
信彦は、1年半ぶりに故郷に帰って来ました。
雑貨屋の前のバス停を降りて、自宅に歩き出しました。青空に鳥海山が凛々しくそびえ、辺り一面には黄金色の稲穂が輝き、刈り入れの時を待っていました。
「ああ、やっと故郷に帰った!由美ちゃんはどうしているだろう?今すぐにでも逢いたい!!」
信彦は、昨年の5月に御嶽神社で由美子に逢った時からを回顧しながら、畦道を歩きました。
御嶽神社では、総一郎は由美子に確かに言いました。『二人の結婚を両親は反対しているけど、僕は必ず由美子ちゃんと結婚するからね。これからは、何があっても信じ合おうね!』由美子の手を強く握り、信彦は心の底から声を搾り出しながら話したのを昨日のように思い出しました。
総一郎は翌日東京のアパートの戻り、しばらく普通どおりに生活していましたが、6月に入ったころから咳と微熱が続くようになりました。風邪かと総一郎は仕事の忙しさにかまけて放置していました。しかし、そのうち食欲も低下した総一郎はただの風邪ではないと心配になり、休暇を取り近くの医院を受診しました。初老の医師は今までの様子を聞いたり、聴診器を胸に当てたりしながら言いました。
「大きな病院で一度診て貰いなさい。紹介状を書いてあげるから。」
翌日会社に事情を話し、アパートから歩いて行ける程の距離にある大きな病院を訪れました。およそ半日かかった受診の結果、即日入院となりました。病名は、肺結核とのことでした。レントゲンを撮り、痰も採取されました。なんでも結核菌が検出されるかどうかの結果が出るまで1ヶ月も掛かるとのことで、もし結核菌が陽性なら周囲の人にうつしてしまうので、結果が出る前から入院の必要があると50歳前後の呼吸器科の医師は告げました。
総一郎は、あることがその時とても心配になり医師に尋ねました。
「先生、田舎の両親に手紙を出すことは、問題ないでしょうか?」
医師は、もし結核菌が陽性なら例え手紙でも感染する可能性がゼロではないから、それは許可できない。手紙でなくとも電話があるじゃないかと無情な返事でした。
医師に診断書を依頼し、会社には長期休暇のお願いと診断書の提出の連絡をし、また実家の両親にも事情を電話で伝えました。母は驚きながらも、月に何度か栄養のあるものを女中のお里に届けさせるから、また、アパートの掃除もついでにさせると言い、今の時代結核は何の心配もない病気だと、総一郎を安心させようと何度も念を押しました。
結核の入院生活は、服薬の他には何もすることがなく、ただ安静にして栄養のあるものを食べるということだけでした。余りの退屈に会社の同僚に電話をし、欲しい本を10冊程度買い求めて送ってもらい、読書三昧の総一郎でした。
検査の結果やはり結核菌は陽性で、一年近くの入院生活になるとの冷たい医師の言葉に、総一郎は愕然としました。
ただ、由美子に今の状況を知らせなければと、それだけが心配でした。手紙を出すことを禁じられ、その上で周りに知られずに由美子に連絡を取ることは難しいことでした。ただ、御嶽神社で手を取りながら話した、信じ合おうと言った言葉だけが唯一救いの総一郎でした。
総一郎にある名案が浮かびました。十日に一度は訪れてくれる女中のお里に、何とか事情を由美子に伝えて貰うということです。でも直接お里に会って話せないので、担当の看護婦に頼みました。まだ20代の若い看護婦は、ニヤッと笑って、分かりましたよ!と、大きな声で返事をしてくれたのでした。
もう入院して4ヶ月になり、師走の季節となりました。女中のお里を通じ、由美子にはこの病院に入院していることが分かっている筈なのに、一向に何の連絡もありません。手紙も届かないのです。これはどうしたことか、総一郎には不思議でなりませんでした。総一郎は、由美子の自分に対しての愛情に絶対の自信を持っています。
「何か事情があるに違いない。この病気が治るまでの辛抱だ。由美ちゃんの気持は変わらない筈だ。それだけは、疑ってはならない。」
年が明け、春が来て、梅雨の季節になった頃、総一郎は医師から結核菌の排出が見られないのでもうすぐ退院だと知らされました。
しかし、最近の総一郎は空腹時にみぞおち付近が痛み、胸やけがし吐き気もみられるようになっていました。ある日、吐き気がしてトイレに行くと、黒褐色の血と咀嚼物とを一緒に吐きました。吐血です。備え付けられた呼び鈴を鳴らすと、看護婦がすぐやって来て、トイレを見るなり慌てて医師を呼びに走りました。
結局、胃潰瘍と診断され、結核病棟からは解放されたものの、再び入院生活を続けることになりました。
総一郎は、由美子から何の連絡もないことに、大きな不安を抱くようになっていました。結核菌の排出が陰性となってから、訪ねてくる女中のお里に手紙の投函を頼み、その数は既に6通を超えています。それなのに、何の返事もないのです。総一郎は、由美子の愛を少しも疑ってはいませんが、この状況は信じられず、ストレスのみを増大させました。
消化器病棟へ移ってからは、女中のお里が総一郎のアパートに泊まり込みながら毎日病院に通い、身の回りの世話を焼いてくれました。
押し寄せる不安と闘いながらも手術をせずに完治し、医師から退院の許可を得たのは、秋田の田舎ではもう直ぐ稲刈りが始まるという9月の末でした。退院の日、総一郎とお里は総一郎のアパートに戻りました。お里は夕飯の支度をし、部屋を片付けると、秋田の総一郎の家に帰って行きました。要らなくなった荷物を持って帰り、また総一郎の部屋の掃除やら準備があるからというのがその理由でした。
総一郎は畦道を歩きながら、由美子に逢いたいという逸る心を抑えきれずに、逢ったら何から話そうかと思案していました。
最終回 昭和51年9月下旬
総一郎の今回の帰省については、温情ある上司から来月から出社すればよいから、田舎で少し静養して来なさいとの指示を受けていました。
凛々しくそびえる鳥海山は総一郎の帰りを喜んでいるような想いがしました。また刈り入れ前の黄金の稲穂は、都会の喧騒から離れた総一郎に寛ぎを、そして生きる素晴らしさを教えてくれるようでした。完治した胸に、思いっきり吸った空気は、総一郎の体の末端まで酸素が行き渡り、血管さえも喜んでいるかのようでした。
でもそれは一時でした。一刻も早く由美子に逢い、今までの不思議と言うより異常な事態の真相を知り、そして由美子との愛を再確認したいと総一郎は考えていました。場合によっては、今回は両親との縁を切っても、由美子との結婚を宣言する覚悟でした。
畦道を過ぎると集落に入りました。総一郎の実家はもう直ぐです。そう言えば父親の太門の顔を見るのも久しぶりでした。母のしのぶは、結核病棟から消化器病棟へ移った時に来てくれ、とても心配してくれたその時以来です。ですがそれでも3ヶ月振りです。症状や回復度については、お里が逐一電話で報告をしていたようでした。
やっと実家に着いた総一郎を母親のしのぶは、嬉しそうに総一郎の顔を見、それから全身に目をやりました。
「総一郎、良かった。本当に良かった!」
しのぶの目から、一粒の大きな涙が頬を伝わり落ちました。
「夕飯まで、離れの部屋でゆっくりしていたら。お父さんも夕方には帰って来るだろうから。」
総一郎は、お里の姿が見えないことに気付き母に尋ねました。
「そう言えば、お里の姿が見えないようだけど?お里には、随分世話になったよ。こうして元気になれたのも、お里のお蔭だよ。」
総一郎は、お里にお礼を言いたかったのです。母は、一瞬驚いたようでしたがそれでも落ち着いて言いました。
「お里は、実家に昨日帰ったよ。お前の荷物を片付けたり、部屋の掃除をしてから、暇をくれと言い出したんだ。お前がいないと、総一郎も寂しがるし、もうしばらくいてくれないかと話したが、どうしても家に帰りたいと言い張って帰ってしまったんだ。」
いつもは歯切れの好い話し方をする母に似つかない、苦渋のような表情が見て取れました。総一郎は、何か胸騒ぎを覚え「少し、部屋で休むから。」と母に告げ、離れの自分の部屋に向いました。
部屋に戻った総一郎の机の上に、白い封筒が置かれ、その傍には何やら包まれた風呂敷が添えられていました。封筒の表には『総一郎さまへ』と書かれ、裏には『お里』と記されていました。
ハサミで切るのももどかしく、指で切り裂きました。
総一郎さまへ
総一郎さまが全快し、お里は何より嬉しくてたまりません。総一郎坊ちゃんが、5歳の時から私はこの家に奉公に上がり、主に総一郎ぼっちゃんの身の回りのお世話を言い付かっておりました。総一郎坊ちゃんが、ここまでご成長され私の役目も終わりました。
今回、ご奉公を辞めることは辛いのです。近い将来、総一郎坊ちゃんのお子様たちの面倒をこれからは仰せつかれたらと期待していたほどです。
ですが、私にはその資格がないのです。私は、総一郎坊ちゃんが大好きです。総一郎坊ちゃんには、本当に幸せになって欲しいというのが、私の一番の願いです。
でも、私は総一郎坊ちゃんを裏切ってしまいました。心では、総一郎坊ちゃんの幸せを願いながら、その逆のことをしてしまいました。
私は、昨日までは平静を装い、総一郎坊ちゃんの面倒を見させて頂きましたが、本当は申し訳なさで一杯でした。何もかも話してしまいたい衝動に何度も駆られましたが、その度に喉元で何とか抑えました。
これから私が拙いことばで書きますことは全て真実です。ですが、このことは、総一郎ぼっちゃんを不幸に貶めるためにしたことではありません。そのことは、命に代えても誓うことが出来ます。
そして、総一郎坊ちゃんのご両親様も同じです。総一郎坊ちゃんの幸せを第一に考え、僅かでも自らの利益のためにしたことではありません。どうぞ、分かってください。
総一郎ぼっちゃんは東京におられたのでご存知ないことですが、去年の8月頃総一郎坊ちゃんが、仁賀保の社長の家に婿養子に入るという噂が流れました。多分、由美子さんの耳にも届いた筈です。
この噂はご主人様の言い付けで、私と使用人数名が商店での買い物や、盆踊りの祭りの時などに、それとなく言い触らしました。もちろん目的は、由美子さん親子にこの噂を流すためです。そうすれば、可哀そうではあるけれど、由美子さんも総一郎坊ちゃんを諦めるだろうと考えたのです。
私も他の使用人も初めはお断りをしました。当たり前のことですが、総一郎坊ちゃんを悲しませること等出来ないと、皆口々にご主人様に申し上げました。しかし、ご主人様の言うことには、総一郎と由美子さんが一緒になっても、決して幸せにはなれないというのです。人には、分相応というものがあり、今までの暮らしを急に変えることは難しい。由美子さんがこの家に嫁に来ても、お前たちの面倒を見ることはおろか、この家の格式に沿った多くのしきたりを学ぶことも大変なことだ。ただお互いが好きなら、誰でも良いという訳には、当人の為にも、敢えて言わせてもらえばこの家の為にもならないのだと仰るのです。
私らは、学識と言うものが無いもので、ご主人様のいうことは尤もな事なのだろうと納得してしまったのです。由美子さんが、この家の嫁になって辛い想いをさせるのなら、今のうちに別れさせてあげる方が由美子さんのためなら、それが強いては総一郎坊ちゃんの為なら、ご主人様のご指示に従おうと皆で話し合い、実行に移しました。
聞いた話によると、この噂を聞いた由美子さん親子は大分衝撃を受けたようです。その後、由美子さんのお見合いの話しが急にいくつか持ち上がったと聞いています。母親のふみ子さんは、見合いが嫌ならこの家から出て行けとまで由美子さんに迫ったと聞きました。私はその噂を聞いた時、涙が流れてなりませんでした。由美子さんの気持ちを考えると、自分のしたことが果たして良かったのかと、何日も眠れませんでした。
私のしたことは、それだけではありません。もっともっと総一郎坊ちゃんに酷いことをしたのです。とても会ってお話しする勇気がありませんので、総一郎坊ちゃんがこの手紙を読むと思われる頃、私は実家近くの神社でお許しを乞うため、そしてこれから総一郎坊ちゃんと由美子さんがそれぞれの道に分かれても幸せになって頂けるよう、宮司さんにお祓いをして頂くつもりです。そうでもしないと、私は申し訳なさに生きて行くことが辛くてなりません。
もっと酷いことについて話します。奥様からお願いされたことなのですが、総一郎坊ちゃんが肺結核と分かった時に、10日に一度栄養のあるものを病院の隔離病棟に届けるように指示されました。そのついでに、病院から総一郎坊ちゃんのアパートの隣にある酒屋の大家さんから鍵を借り、部屋の掃除も頼まれました。それだけなら何の問題もないのですが、アパートにもし由美子さんの手紙などが入っていたら総一郎坊ちゃんに渡さず、捨ててしまうように言われました。それはあまりに酷いことと思い、こっそり坊ちゃんに渡してしまおうと考えました。
そう考えて、病院に行く前に総一郎坊ちゃんのアパートにより、郵便受けを見ると10通くらい由美子さんからの手紙が入っていました。私は、バックに入れながら、総一郎さんに渡すつもりでした。病院に着いて、受付で果物などを渡す時に、由美子さんからの手紙の袋も一緒に渡そうとした瞬間、二人を別れさせるのは由美子さんと総一郎坊ちゃんのためだというご主人様の言葉を思い出し、取り出そうとした手を躊躇させ、結局持ち帰ってしまいました。
この次には必ず渡そうと思っていましたが、次の訪問日にも数枚の由美子さんの手紙が郵便受けに入っていました。でもやはり持ち帰ってしまいました。こうして由美子さんの手紙は総一郎坊ちゃんには1通も渡さず、全て持ち帰ってしまいました。持ち帰った手紙は風呂敷の中に入っています。もちろん封を切らないままです。全部で20通は軽く超えていると思います。本当は、捨ててしまいなさいとのご命令でしたが、どうしても出来ずに持ち帰りました。
もう一つ、もっと酷いことを致しました。総一郎坊ちゃんが隔離病棟を出てから、投函を頼まれた由美子さん宛ての手紙をポストに入れないままに、捨ててしまいました。ご指示は奥様ですが、捨てたのは私です。
私のしたことで、総一郎坊ちゃんと由美子さんの連絡を絶ちました。このことで、どれほど由美子さんには辛い想いをお掛けしたことでしょう。また、総一郎坊ちゃんを裏切ってしまいました。
聞くところによると、結局由美子さんは周りの圧力に負け、総一郎坊ちゃんと別れることが、総一郎坊ちゃんやお互いの親のためになるのだと、つい10日前に婚礼を済ませたそうです。婚礼の日には、どうしても御嶽神社に別れの挨拶に行くと言い、拝殿の前で涙を流したそうです。
私は、総一郎坊ちゃんに合わせる顔がありません。死んでお詫びしたいくらいです。でも、きっといつか総一郎坊ちゃまにも、ご両親を許し、この日が懐かしく思われる日が来ることと信じています。
どうか、どうか1日も早く立ち直り、明るい将来のために力強く歩まれることを津軽海峡を目前にした北の地で祈っています。 お里
お里の長い手紙を読み終えた総一郎は、御嶽神社に向って走り出しました。御嶽神社の拝殿の前の賽銭箱には、つい10日前に訪れた由美子の和紙で包まれたお賽銭がそのまま置かれていました。総一郎は、そっと和紙の包みを手に取り自らの頬に当て、涙を流し続けました。
時は流れ、昭和の時代も過ぎて、今日は平成30年の1月3日です。仁賀保の会社の会長となり、また市会議員のバッジを着けた総一郎は、秘書の運転する車で約40年ぶりに御嶽神社を訪れました。
車で待つように運転手に伝え、降りようと足を踏み出したその時、拝殿の前に孫と思われる小学生と一緒の総一郎と同い年位の、身なりの良い女性の姿が目に入りました。
財布を手に持って拝殿に近づく総一郎に、女性は振り向きました。齢を重ねたその女性には、昔の面影が変わらずに残っていました。
「総一郎さん?総一郎さんでしょ?」
声を掛けたのは由美子でした。二人の目が合った時、二人の目には涙が光っていました。
雪で覆われた鳥海山は、昔のままの姿で青空に輝いていました。 おわり