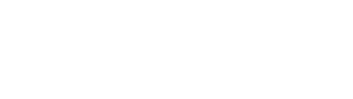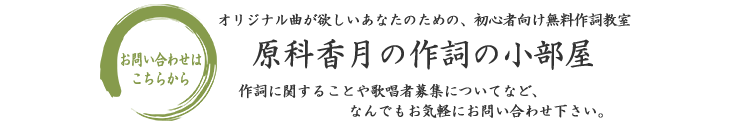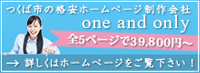創作の小部屋「30代派遣男の終活」前編
2021年10月21日
 30代派遣社員の終活 前編
30代派遣社員の終活 前編
昨日は、とても良い天気だったので、暫く振りにデジカメを持って筑波山と霞ケ浦方面に車を走らせました。筑波山に向かう途中、沢山実った柿の木を見つけましたので、脇道に入って撮影しました。後方には、青空に筑波山がそびえていました。下の画像は柿を拡大して撮りました。
赤く見えるこの実は、カラスウリです。カラスウリの花は、関東では6月頃から見られるようになります。日が暮れると開花し、朝には閉じてしまうそうですが、夕方の散歩で真っ白いレースのような花を見たことがあります。
コロナ禍の影響もあり、出かけるのがどうしても億劫でした。最近は東京でも新規感染者が50人を切るという素晴らしい回復ぶりに、心がつい踊ってしまいました。私の住む茨城県でも1桁の感染者が続き、とても安心できる状況となりました。
ですが、これから冬を迎え第6派も危惧されております。これまで通りマスクの着用と手洗いの慣行を忘れてはならないと思います。
31日投開票の衆院選についてですが、各党の政策は私の目から見ても、国民に迎合した財源の裏付けのない、バラマキ合戦という印象を受けます。消費税を下げるとか、失くすとか、本当に可能なのでしょうか?私たちは、上手い宣伝文句に振り回されず、心眼で尊い1票を投じなければならないと思います。
今回の創作の小部屋は、とても悲観的な内容となっているかも知れません。ですが、現実にコロナ禍以前から貧しさに苦しみ、将来に希望が見えない方が大勢いることも事実です。今回は30代の派遣社員を主役に物語を作ってみました。
30代派遣社員の終活 前編
【倒産という悲劇】
私は30代後半の派遣労働者だ。北関東の田舎で育った私は、小さな町工場勤めの両親の次男坊として生まれた。
高校を卒業した私は、東京の多摩川に近い、ある部品製造会社の事務員兼作業員として就職した。事務の仕事が主だが、休みの人が出たりした場合は現場に入るという条件だった。折しも就職氷河期と言われた時代だったが、運よく仕事に就くことができて私は嬉しかった。
終戦から5~6年後に生まれた私の父は、高度経済成長期の恩恵を享受した。その父の口癖は「真面目に仕事に励めば、平凡ではあっても、老後まで世間並みには暮らしていける」だった。
就職した私は、決して高給と言えなかったけれど、特に不満もなかった。田舎者の私に職場の仲間はとても親切だった。そう言えば、みんな地方出身者ばかりだった。会社の狭い寮で共同生活をした。
ただ職場には、若い女性はおらず、女性と出会う機会はなかった。20代半ばになっても、女友達という言葉に縁はなかった。人見知りをする私は、ネットでの出会い系サイトなどに興味はなかった。結婚し子供を授かっても分かれる人が多い世情からか、田舎の両親も特に結婚について口を挟んで来ることもなかった。
そんな私の生活が一変したのは、私の会社の売り上げ額が8割を占める取引会社からの、納入品の大幅な値引き要請が事の発端だった。確かに不景気で、どこの会社も青色吐息だった。社長は値引きの圧縮を何度もお願いした。しかし取引先からは、駄目なら他の業者に切り替えるとの一言のみであった。
確かに、一つの企業に自らの会社の命運を託す社長の経営方針に無理があった。だがそれにも事情はあったらしい。とにかくこの状態を改善すべく、事務の私までも含めて新規取引先の開拓に汗を流した。努力は、いつも報われるとは限らない。足元を見て、原価割れをするような要求をしてくる会社も多かった。
業績はたちまち急降下し、原料の支払いにも困窮するようになった。社長の顔色はさえなくなり、それから数か月のうちに2度目の不渡りを出し倒産となった。私も含めて従業員は、大きなショックを受けた。僅かながら、社長の人柄からか退職金が出た。寮を出て、お金を出し合い、寮の仲間とアパートを借りた。その頃私は既に30代に入っていた。
【ハローワークに通って】
過去をいつまでも引きずってはいられない。今後の生活のため離職票他の書類を揃えると、直ぐにハローワークへ失業手当金の申請をした。すると、程なくして指定の口座に給付金が支払われた。初めは働かずに、また口うるさい年配の女性との煩わしい会話からも解放され、この失業給付金は有難かった。
だが、しばらくすると毎日の時間の消費が苦痛になって来た。確かに、仲間と公園を散策をしたり、ベンチで弁当を食べたりして過ごすのは楽しかった。また、多摩川での小魚釣りもとても新鮮だった。だけれども、同じ仲間と四六時中いると、やがて息苦しくなった。多くの人が労働している太陽が燦々とふり注ぐ時間帯に、時間の消費の仕方に悩んでいる自分たちが酷くみじめに感じられるようになった。倒産前の会社の時は、月曜日の朝は憂うつだった。だが、今はその辛さが恋しくて堪らない。
仲間と共にハローワークを頻繁に訪問した。高卒で何の資格も特技もない、この私でも採用されそうな会社を探した。だが、それらは全て派遣社員の求人ばかりだった。正社員の募集は目を凝らしてみても、見当たらなかった。あるにはあったが、薬剤師とか研究員などで自分には無縁の職種のみだった。仲間はそれぞれの職を見つけて、一人二人と派遣会社への就職を決めていった。
【派遣労働者となって】
失業から初めて就いた私の仕事は、大豆を原料とした製品の工場だった。この会社で使用する薬品が私の体質に合わなかったのか、二日目には左腕がかぶれて真っ赤に腫れ上がった。10日ほど我慢して働いたが、この小さな会社には、働く者の健康にまで配慮する余裕はなかったようだ。せっかく就いた仕事だったが断念した。
次に就いた仕事は、ある大手のコンビニに納品している食品会社だった。派遣会社の担当者によると、流れ作業でパン生地の上に、ある食材を置くだけの作業という。簡単で誰にでも出来るとのこと。勤務初日、私は工場の担当者から簡単な説明を受けた後、さっそく作業服に着替えさせられ現場に向かった。その後、数分も経たないうちに、私は驚くこととなった。
何の説明もなく、もう既に流れているラインに立たされたのだった。何をどのようにするのか訳も分からず、周りを見渡した。隣で作業をしていた人から、一言二言要領を聞いた。流れるラインに追い付かず、焦った。本当に焦った。初日は、要求されている半分程度も働けなかったと思う。この作業は、首を下に傾けたまま、足を1歩も動かすことはない。
それでも私は負けなかった。2週間も経った頃だろうか?やはり派遣社員だろうと思われる中年の女性が私の方を見て言った。
「あの人、凄いね!まだ入ったばかりなのに、他の人よりずっと早いよ!」
他の数人の女性からも感嘆の声が上がった。だが、その前後あたりから、私の指と首の筋は悲鳴を上げ始めていた。腱鞘炎のように指がこわばり、時々硬直して自分の意志では自由にならなくなった。夜、布団の中で寝がえりを打つと首が痛んだ。
そういう状態のまま頑張っていた私を、そのラインの責任者は認めてくれたのか、別のラインに移動を命じた。責任者は上機嫌で時給を上げてやると言った。しかし更にきつい労働だった。ラインの流れる速さも、瞬時に行う作業の量も現在の私の能力を超えていた。
それから数日後、私はもうこれ以上この仕事を続けて行くのは無理と判断し、腰痛のため退職したいと派遣会社の担当者に伝えた。私は仕事が嫌いなわけではない。アパートでブラブラしているのはたまらなく辛い。それが分かっていても、止むを得なかった。派遣会社の担当者は「ああ、そうですか」とだけ答えた。
夜、アパートの仲間と愚痴を言い合ったが、やはり派遣労働者への処遇は酷いもので、最低賃金の上、社員が嫌がるような内容の仕事が多いようだ。 つづく